「AI(人工知能)」という言葉が日常でもよく聞かれるようになった現代。しかしそのルーツをたどると、1950年代から続く長い研究の歴史があることをご存知でしょうか?
AIの歴史の中でも、特に注目すべきなのが「第一次AIブーム」と呼ばれる時期です。この時代は、人工知能という新しい分野が生まれ、世界中の研究者が「機械が人間のように考える」ことを真剣に追い求め始めた重要な転機でした。
この記事では、第一次AIブームがいつ起こったのか、どんな技術や考え方が注目されたのか、そしてなぜブームが終わってしまったのかをわかりやすく解説します。
あわせて、その後のAIブームや、英語学習への応用についてもご紹介しますので、AIの歴史に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
第一次AIブームはいつ起こった?

1956年の「ダートマス会議」でAIの概念が初めて提唱され、その後1960年代から1970年代初頭にかけて続いたAI熱狂の時代は「第一次AIブーム」と呼ばれています。
ダートマス会議では、アメリカの計算機科学者ジョン・マッカーシーが初めて「Artificial Intelligence(人工知能)」という言葉を提案したことから、AI研究の本格的なスタートが切られました。
この時代、「人間のように考える機械をつくる」という夢を掲げて、多くの研究者が論理・数学・言語などの分野で精力的に取り組みました。初期のAIプログラムは、迷路の問題を解いたり、簡単な会話をしたりするものでしたが、「機械も知能を持てるのでは?」という期待が急速に高まっていきました。
当時のAI研究は、大学や研究機関を中心に進められ、コンピューターという新しい技術に注目が集まりつつあった社会とも相まって、まさに時代の最先端として注目されたのです。
第一次AIブームが終わった理由
第一次AIブームは大きな注目を集めた一方で、長くは続きませんでした。その主な理由は、当時の技術では「思ったような知能をAIに持たせることができなかった」からです。
当時のAIは、主に「推論」や「探索」といった論理的な処理に頼っており、あらかじめ決められたルールや条件にもとづいて動作していました。そのため、単純な迷路を解くことはできても、現実のように曖昧で複雑な状況には対応できなかったのです。
また、コンピューターの処理能力や記憶容量も限られており、研究の進展にも限界がありました。その結果、「AIにはまだまだ実用性がない」「期待が大きすぎた」との批判が高まり、政府や企業の研究資金も縮小しました。
そして、研究自体が停滞する「AIの冬」の時代が訪れることになります。
第一次AIブームで重要なキーワード
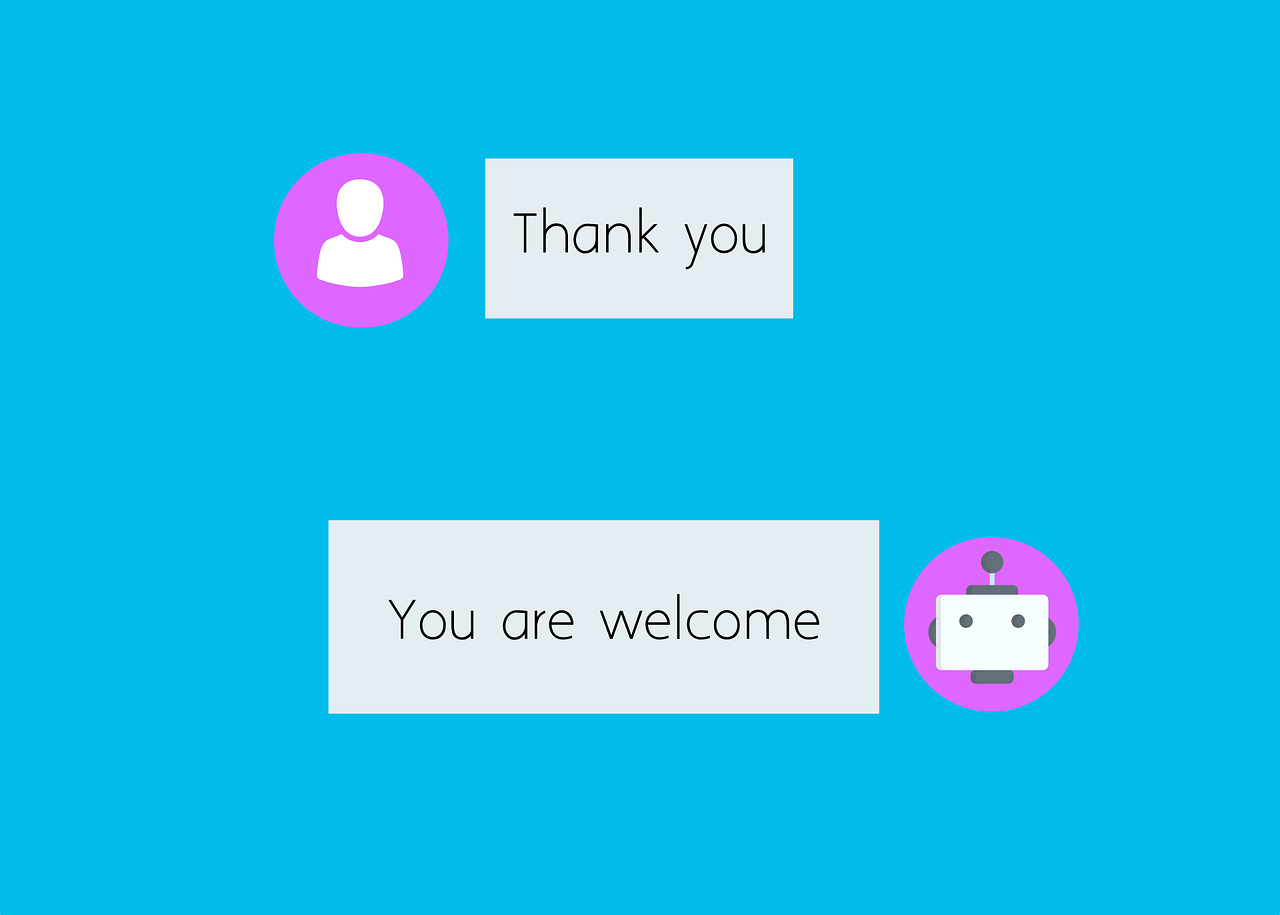
第一次AIブームを理解するためには、当時のAI研究を特徴づけるいくつかのキーワードを知っておくとよいでしょう。
ここでは代表的な3つの概念をご紹介します。
推論と探索
第一次ブームの頃のAIは、「もし~ならば~する(if-then)」というルールにもとづいて、「推論」と「探索」という2つのプロセスに重点が置かれていました。
「推論」は論理的に結論を導くこと、そして「探索」は複数の選択肢から正しい解を見つけ出すことを意味します。たとえば、チェスのようなゲームで最善の手を探すといった処理に使われました。
ただし、この方法は問題のパターンが非常に多い場合や、途中に不確定な要素がある場合には対応できないという弱点がありました。
ELIZA(エライザ)
1966年に登場した「ELIZA(エライザ)」は、世界初の対話型AIプログラムとして有名です。
あらかじめ用意された会話のパターンにもとづいて、あたかも人間と話しているような返答をする仕組みで、多くの人々に「AIと会話できる時代が来た」と思わせました。
とはいえ、エライザの会話は実際には単純なルールに従っているだけで、相手の気持ちを理解しているわけではありませんでした。
そして、ELIZAの限界が露見したことも、第一次AIブーム終焉の一因となりました。
トイプロブレム
当時のAI研究では、現実の複雑な問題を扱うのではなく、比較的単純な「おもちゃのような問題(トイプロブレム)」を題材にすることが多くありました。たとえば、積み木を積み上げる作業や、単語を並び替えるゲームなどです。
当時のAIは、これらの課題では高い成果を上げられたものの、現実世界のように不確定な要素を多く含んだ問題には応用が利きませんでした。
その結果、「研究の成果が社会に活かされない」として批判の対象になり、ブーム終焉の原因の1つとなりました。
第二次、第三次、第四次AIブームとは?
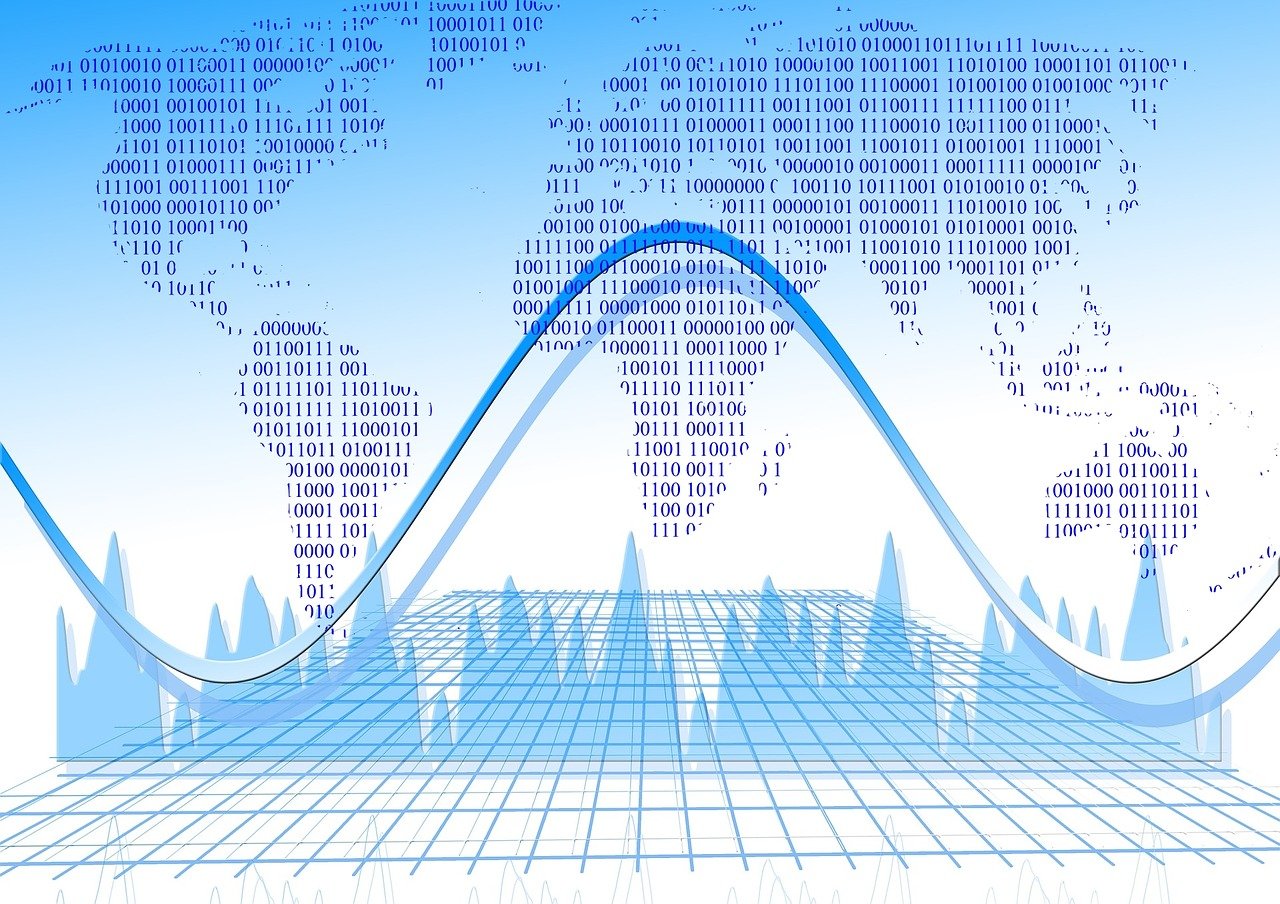
第一次AIブームの終焉からしばらくの時を経て、AIは再び注目を集めるようになります。
ここでは、第二次AIブーム以降の流れについて、それぞれ簡潔に振り返っていきましょう。
第二次AIブームの始まりと終わり
第二次AIブームは1980年代に始まりました。
この時期のAIは、医療や製造業など特定分野に特化した「エキスパートシステム」によって実用化が進んだのが特徴です。専門家の知識をコンピューターに組み込み、診断や故障検出などを自動化できることが注目されました。
しかし、知識の入力には膨大な時間と人手がかかり、環境の変化に弱いという問題が露呈しました。
さらに、コンピューターの性能がまだ追いついていなかったこともあり、やがて限界が見え、1990年代には再び「AIの冬」が訪れることになります。
第三次AIブームの始まりと終わり
2000年代後半から始まった第三次AIブームは、ディープラーニング(深層学習)とビッグデータの登場によって実現しました。
特に2010年代に入ってからは、画像認識、音声認識、言語処理などの分野でAIの精度が大きく向上し、実生活への導入が一気に進みました。
2015年には囲碁AI「AlphaGo(アルファ碁)」がプロ棋士に勝利し、「AIが人間を超えた」として世界中で話題になりました。その後もAIは検索エンジン、翻訳アプリ、スマートスピーカーなど、私たちの暮らしの中に急速に広がっていきました。
現時点でもこの第三次ブームは続いており、「終わった」という見方はされていません。むしろ、生成AIの登場により、新たなフェーズに移行しつつあると考えられています。
第四次AIブームはいつから?
現在は第三次AIブームの最中にありますが、特に進化が目覚ましい近年を独立させて「第四次AIブーム」と呼ぶこともあります。その発端となっているのが「生成AI」と呼ばれる分野の急成長です。
ChatGPTやStable Diffusionなど、文章や画像などのコンテンツを自ら生み出すAIが登場し、これまでの「識別するAI」から「創造するAI」への進化が注目されています。
また、AIが人間のようにマルチタスクをこなす「汎用人工知能(AGI)」の研究も進みつつあり、今後のAIはさらに社会を変える力を持つと考えられています。
英語学習でもAIがブームになっています
AIの進化は英語学習の分野にも大きな影響を与えています。
たとえば、AIによる発音判定機能を使えば、自分の発音とネイティブスピーカーの違いを即座にチェックできます。また、英文添削ツールや会話トレーニングアプリもAIによってより精度が高く、自然なやり取りが可能になりました。
学研のオンライン英会話「Kimini英会話」でも、AIと講師の組み合わせによるハイブリッドな学習が取り入れられています。
英語学習をサポートするAIチャットBotが、英語の先生や会話のパートナー、予習・復習サポーターとしてあなたの質問や相談に回答します。
スマートフォンのホーム画面に追加すれば、アプリのようにワンタップでアクセス可能で、スキマ時間の活用にもぴったりです。
英語を効率よく学びたい方は、日々の学習にAIを活用してみてはいかがでしょうか。
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
まとめ
今回は、第一次AIブームについて、詳しく確認してきました。
第一次AIブームは1960年代に起こり、「推論と探索」や「ELIZA」などの技術が注目を集めました。しかし、現実の複雑な問題には対応できず、やがて研究や資金が停滞し、ブームは終焉を迎えました。
その後もAIは「第二次」「第三次」といったブームを経て進化を続け、現在は「第四次AIブーム」とも言える生成AIの時代に突入しています。
AIの歴史を知ることは、これからの社会や仕事、教育のあり方を考えるヒントになります。今回の内容を参考にして、今後もAIの進化に注目しつつ、賢く活用していきましょう。


