AI(人工知能)は近年急速に進歩し、社会の様々な場面で活用が進んでいます。
本記事ではAIの歴史的発展を踏まえ、現代の状況を整理しながら、AIが未来の仕事や社会に与える影響について詳しく解説していきます。
AIの過去と未来がマルっとわかる内容なので、さっそく見ていきましょう。
AIの発展と歴史
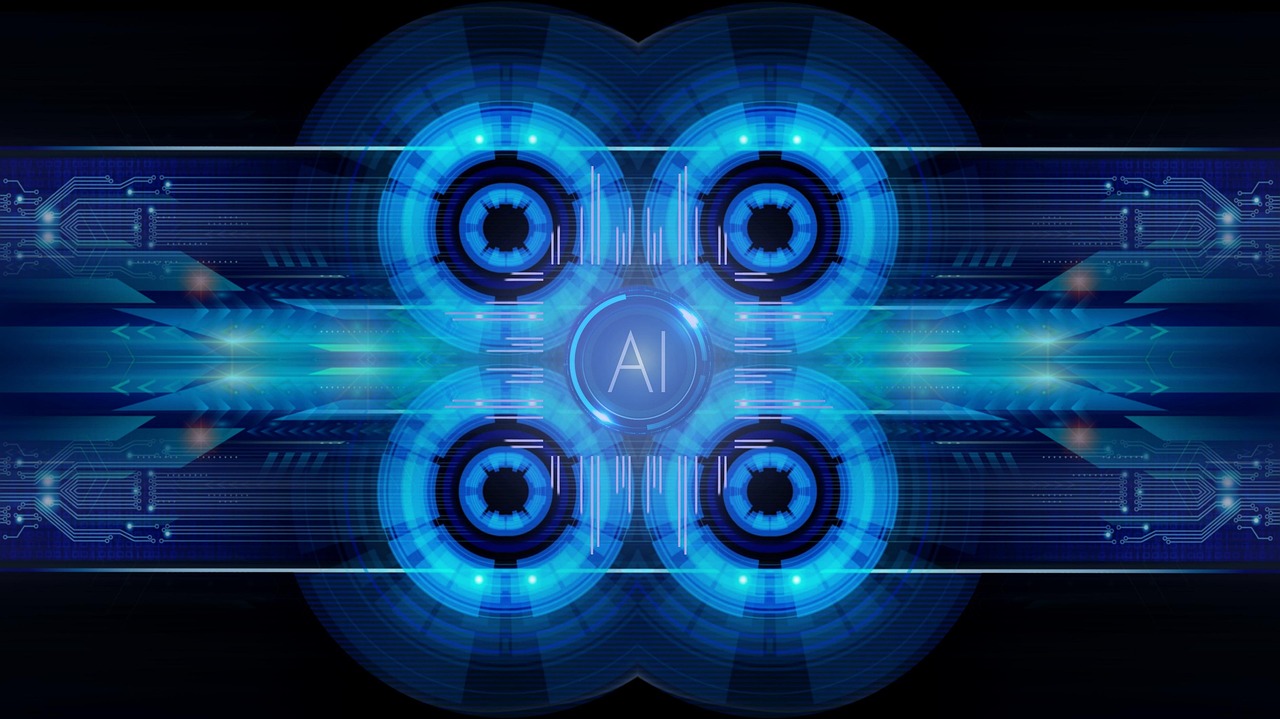
AI(人工知能)の歴史は実はここ10年のようなスパンではなく、もっと前から話が始まっています。
まずはそんなAIがどのようにして現在に至ったのかをご紹介していきます。
AIの起源は1950年代に遡る
結論からいうと、AIの起源は1950年代にまで遡ります。
当時、数学者である「アラン・チューリング」によって研究が進みました。
生成AIの歴史は、1950年代に数学者アラン・チューリングによって提唱された概念に遡ります。チューリングは、機械が人間のような知的な振る舞いができるかを判断する「チューリングテスト」を考案しました。
参考:Adcal
当時のAI研究は、人間のように考えるコンピュータの実現を目指していましたが、計算能力の制約などにより実現可能な範囲が限られていたのです。
近年のAIの急速な発達
近年では機械学習とディープラーニングの登場により、AIの能力が飛躍的に向上しています。
この急速な進歩の背景には、大量のデータの活用、計算能力の劇的な向上、そして新たなアルゴリズムの開発があるようです。
従来はいわゆる「分析」がメインでAIが使われていましたが、現在ではAIが自身の力で「生成」を行えるようになりました。
まさに「ChatGPT」などのツールはこの生成AIに分類されます。
マルチモーダル対応が基本になった
2025年の現在では、生成AIがマルチモーダル対応になりつつあります。
例えばChatGPTでもそうですが、単に何かの情報を検索して出してもらうだけでなく、画像を生成したり、音声を分析したりしてもらうことが可能です。
マルチモーダルとはまさにこの「複数の形式」を指しており、日々その対応範囲は広くなってきています。
AIの発達が仕事に与える影響

日々利便性があがってくる世の中で、Aiの発展が実際にどの程度仕事に影響を及ぼすのでしょうか。
分野によっては既にAI化が進んでおり、仕事を実際に奪われてしまった人たちも存在します。
そんな現在起こっている人間とAIとの関係性について見ていきましょう。
AIが単純作業を代替する
AIの進化により単純作業を中心とした業務の多くが自動化される可能性が高まっています。
いわゆる「これ自分じゃなくてもできるよな・・・」といった作業がAIに置き換えやすいです。
例えば、データ入力作業や翻訳などは一番分かりやすい例でしょう。
今まではそのスピードの速さや、翻訳の質などが評価軸となり、市場としても需要がありました。
しかし、現在では全てAIで置き換えが可能なうえ、上位互換ともいえるパフォーマンスができることから、仕事を代替できるようになってきているのです。
独自性や感情の読み取りは苦手
単純作業はAIに置き換えられるようになった一方で、より一層「独自性」が重要視されるようになってきました。
例えば、英語の翻訳でいえば「その人らしさ」が一つの価値になっています。
AIに頼めば100点満点に見える翻訳が可能です。しかし、それは「正解」ではあるものの、若干のロボット感が残っていたり、「実際は使わないけど意味は伝わる言葉」で構成されていたりします。
また、感情的な部分は読み取ることができないので、文法的にはあっていても、失礼な文章を書いてしまうようなケースもあるのです。
AIと共存する新しい働き方
だからこそ現在ではAIと共存する新しい働き方が重要になっています。
データ入力などの独自性を出しにくい分野はどうしても存在する一方で、例えば翻訳業ではAIとの共存によって効率化が可能です。
具体的には、一次翻訳をAIに丸投げしてしまいます。その後、整合性チェックを行い、自分なりに文章を校正するようなイメージです。
文章を自分一人で1~100まで翻訳しないといけなかったところを、90まではAIに任せて残りの10を人間が調整するような動きが共存によって可能になります。
ちなみに自分の英語力に若干の不安がある場合でも、本サイト「Kimini英会話」で英語を調べることで、校正チェックの質を上げることが可能です。
以下に便利なショートカット登録方法もご紹介しているので、ぜひ登録しておきましょう!
iPhone/iPadの場合
- Kimini英会話へログイン(アカウント作成必須)
- スマホの「共有ボタン」をタップ
- 「ホーム画面に追加」/「ショートカットを作成」を選ぶ
- スマホホーム画面へショートカットが作成
- 「Kimini英会話」アイコンをタップで簡単アクセスが可能
Androidの場合
- Kimini英会話へログイン(アカウント作成必須)
- 右上の「︙」をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 「インストール」/「ショートカットを作成」を選ぶ
- 「インストール」/「追加」をタップ
- スマホホーム画面へショートカットが作成
- 「Kimini英会話」アイコンをタップで簡単アクセスが可能
スマホのホーム画面へKimini英会話を追加することで、ログイン状態を保ちつつ、いつでも情報を確認することが可能です。
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
AIと共に歩む未来社会のビジョン

最後にAIの未来について話していきましょう。
今後どのような社会になるのか、どう生きていけばいいのかをご紹介していきます。
ChatGPT(生成AI)の回答
実際にChatGPTに「AIは今後どのような進化をしていきますか?」と聞いてみました。
AIは今後、大規模化・高精度化が進み、画像や音声などを統合するマルチモーダル化が一般化する。また専門分野への特化、個人向けのカスタマイズも進み、自律的な判断や行動が可能になる。透明性や信頼性も向上し、新産業や社会基盤としてさらに浸透していく。
AI目線だと今後については、制度の向上やより多岐にわたる分野へのマルチモーダル化が一般化されるようです。
より利便性が向上され、人間の仕事がどんどんAIに置き換わるのも、今年や来年のスピード感で行われていくかもしれません。
感情を読み取れるようになる可能性も
現在のAIはデータを元に、二アリーな回答を出すのが得意です。
一方でロボット感がまだまだ抜けないので、感情的な部分については考えるのが苦手となります。
しかし、「未来」という話であれば、ここの弱点が改善するようになるかもしれません。
AIが感情を理解できる様になれば、いよいよ「ドラえもん」のようなロボットが現実になるでしょう。
AIと一緒に暮らし、AIと一緒に働く未来が来るのもそう遠くないのかもしれません。
属人性を高めるのが重要
今後どんどん便利になっていくAIと人間が一緒に過ごしていくためには、やはり「属人性」が重要となります。
「この人じゃないとできない」「この人に任せたい」というような、AIでは代替できない強みへのアプローチです。
例えば、「お笑い芸人」の方達は属人性が強いでしょう。具体的には、狩野英孝さんと狩野英孝さんのコピーで作られたロボットがお笑いライブを実施した場合、同じパフォーマンスは出せるものの、後者には人間目線の「行く価値」を感じにくいです。
これがまさに属人性であり、AIがどんなに進化していっても、人間としての存在意義をしっかりと主張できることが重要となります。
まとめ
こちらの記事ではAIの歴史から、AIの発達が仕事に与える影響。そして、未来についてご紹介してきました。
どんどん便利になっていくような世の中ですが、人間ならではの強みをしっかりと活かしていきましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。


