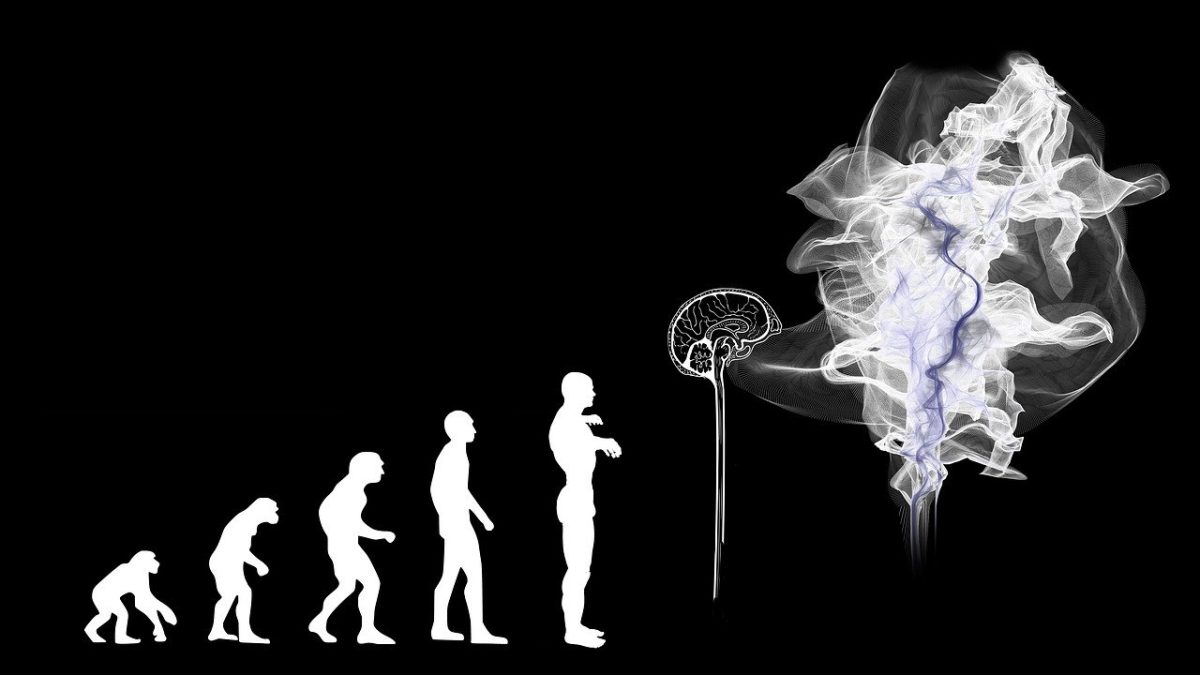今やAIは私たちの生活に欠かせない存在で、スマートフォンのアシスタント機能から、家電、仕事、教育に至るまで、さまざまな場面で活用されています。
しかし、こうしたAIの進化は、一朝一夕で実現されたものではありません。その背景には、1950年代の概念誕生から始まる長い研究の歴史、3度にわたるブームと停滞を経た、技術と知見の積み重ねがあります。
この記事では、AIの起源や進化の流れをわかりやすく解説します。さらに、現代のAIが私たちの暮らしや学び、特に英語学習にどのような影響を与えているのかもご紹介します。
「AIって何?」「いつからあるの?」「どう変わってきたの?」という疑問をお持ちの方は、この記事を読めばきっとスッキリ理解できますよ。
それでは、早速始めていきましょう!
AIの始まり(1950年代)
AIの誕生を語るうえでは、「アラン・チューリング」と「ジョン・マッカーシー」という2人の人物が重要です。
1950年代に彼らの果たした功績について、順に確認していきましょう。
アラン・チューリングによる概念の誕生
1950年、イギリスの数学者アラン・チューリングは論文「計算する機械と知性」を発表し、「機械は考えることができるか?」という問いを投げかけました。
彼は、人間と機械が会話を行い、機械が人間と区別がつかない応答を示すかどうかを試す「チューリングテスト」を提案しました。このテストは、機械の知能を評価する基準として、現在でも広く参照されています。
チューリングテストによって「考える機械」という現在のAIに通ずる概念が生まれたことから、1950年はAI始まりの年とされています。
ジョン・マッカーシーによる「AI(人工知能)」の命名
1956年、米国で開催されたダートマス会議において、ジョン・マッカーシーら研究者たちが初めて「Artificial Intelligence(人工知能)」という用語を使用しました。
この会議は、今日まで続くAI研究の出発点とされ、以降、多くの研究者がこの分野に参入するきっかけとなりました。
第一次AIブーム

AIは、1960年代に世界的な流行を迎え、後のブームと区別して「第一次AIブーム」と呼ばれています。
ここでは、第一次AIブームのキーワードである「イライザ(ELIZA)」と、その後に訪れる「冬の時代」について、詳しく確認していきましょう。
対話型AIの始祖「イライザ(ELIZA)」の誕生
1966年、MITのジョセフ・ワイゼンバウムによって開発された「ELIZA(イライザ)」は、世界初の対話型AIプログラムとして注目を集めました。
これは、あらかじめ設定されたルールに基づいてユーザーの発言に返答する仕組みで、あたかも人間と会話しているかのような体験を提供するものでした。
この技術は非常にシンプルでありながら、多くのユーザーに「本当に会話しているようだ」と錯覚させて話題となり、AI研究の可能性を広げるきっかけとなりました。
AI冬の時代の到来
ELIZAの登場によって注目を集めたAIでしたが、やがて現実的な限界が露呈し、第一次AIブームは終焉を迎えます。
当時のAIは、決まったルールに沿って動く仕組みだったため、現実のような複雑な問題やあいまいな状況にはうまく対応できなかったのです。
その結果、「AIは思ったほどすごくない」という声が増え、研究のための資金も減っていき、「AIの冬」と呼ばれる時代に入っていきました。
第二次AIブーム

1970年代後半から1980年代にかけて、AIはふたたび脚光を浴びることになり、この期間は「第二次AIブーム」と呼ばれています。
この第二次AIブームでは、特定分野に特化した「エキスパートシステム」の登場が大きなトピックとなりました。また、現在のAIに通じる技術的土台もこの時期に築かれていきます。
第二次AIブームの大きな流れについて、以下で順に見ていきましょう。
高度な回答を可能にするエキスパートシステムの実現
エキスパートシステムとは、ある特定の分野における専門家の知識をコンピュータに取り込むことで、問題解決を支援するAIシステムです。
代表例としては、医療分野での診断支援システムや、工業製品の故障診断などが挙げられます。これらのシステムは、従来の汎用的なAIとは異なり、対象領域が限定されていたため高精度な対応が可能でした。
この技術は企業や研究機関で広く導入され、一時期は「AI実用化の時代が来た」と言われ、大きな注目を浴びました。
一般常識をAIに取り込むCyc(サイク)プロジェクトの開始
1984年には、人間の持つ膨大な常識知識をAIに学ばせようとする「Cyc(サイク)プロジェクト」がスタートしました。
これは、AIが常識的な判断や推論を行えるようにすることを目的とし、数百万の知識項目をデータベース化するという壮大な計画でした。
Cycは、その規模と目標の大きさから注目されましたが、膨大な手作業によるデータ入力の必要性や、思ったように成果が上がらないといった課題も抱えていました。
とはいえ、「常識を持ったAI」というビジョンは、のちのAI技術の発展に大きな影響を与えることになります。
ディープラーニングの基礎となる誤差逆伝播法の発表
1986年、カナダの研究者ジェフリー・ヒントンらによって「誤差逆伝播法(バックプロパゲーション)」という新しい学習方法が発表されました。
これは、AIが自分の間違いを見つけて少しずつ修正しながら学習を進めていくという仕組みで、今のディープラーニングの基礎になっている重要な技術です。
この方法により、AIは「試す→間違える→修正する」を繰り返しながら、自分でどんどん賢くなれるようになりました。
当時はまだ活用できる場面が限られていましたが、のちにコンピュータの性能が上がることで、この技術が大きく活かされる時代がやってくることになります。
二度目となるAI冬の時代
しかし、第二次ブームも長くは続きませんでした。
エキスパートシステムは、構築に膨大なコストと時間がかかるうえ、環境の変化に対応しにくいという欠点を抱えていました。
また、誤差逆伝播法の可能性は注目されたものの、当時はまだコンピュータの性能が追いついておらず、大規模なモデルの学習には限界がありました。そのため、1990年代に入ると再びAIへの関心は薄れ、「第二のAI冬の時代」に突入します。
この時期、AIは再び表舞台から姿を消し、一部の研究者によって細々と研究が続けられるのみとなっていきました。
第三次AIブーム

2000年代後半から、AIは再び大きな注目を集めるようになります。それを支えたのが、ディープラーニングの実用化と、インターネットの発展によるビッグデータの活用です。
この第三次AIブームは現在まで続き、私たちの生活にも大きな影響を与えています。
ディープラーニングと社会への広がり
2010年代には、ディープラーニングの技術が本格的に発展し、AIによる画像や音声、言語の認識精度が大きく向上しました。
また、2015年には囲碁AI「AlphaGo(アルファ碁)」がプロ棋士に勝利したことで、AIの能力の高さが広く知られるようになりました。
このブームにより、AIは検索エンジン、翻訳アプリ、スマートスピーカー、医療診断、金融取引など、私たちの日常生活やビジネスのさまざまな場面に急速に取り入れられています。
ビッグデータの活用がAIを加速
第三次AIブームを支えたもう一つの大きな要因が、ビッグデータの存在です。
私たちが普段使っているスマートフォン、SNS、検索エンジンなどからは、膨大なデータが日々生み出されています。 AIはこの大量のデータを学習に活用することで、より正確な予測や判断ができるようになりました。
たとえば、AIが「この商品を買った人はこれも買っている」といったレコメンドを提示できるのは、過去の購入履歴などのデータをもとに学習しているからです。
こうしたビッグデータとAIの組み合わせによって、サービスや商品の提案、検索結果の最適化など、私たちの暮らしがますます便利になっていったのです。
AIは英語学習の歴史も変えつつあります
AIは教育の分野にも活用が進んでおり、特に英語学習ではその力を発揮しています。
たとえば、AIによる発音チェックでは、自分の発音とネイティブの音声を比較し、ズレを指摘してくれます。また、文法ミスや不自然な表現も自動で修正してくれるため、ライティングの精度も上げやすくなります。
さらに、学習履歴に応じて最適な教材や練習問題を提案してくれる機能もあり、無理なく自分のペースで学べるのもAIならではのメリットです。
なお、学研のオンライン英会話「Kimini英会話」では、AIと講師を組み合わせたレッスンを提供しています。
スマートフォンのホーム画面に登録すれば、アプリのようにワンクリックでアクセスでき、スキマ時間にも取り組みやすくなっています。
英語を効率よく学びたい方は、ぜひ日々の学習にAIを取り入れてみてはいかがでしょうか。
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
まとめ
今回は、AIの歴史について詳しく確認してきました。
AIは、1950年代にその概念が提唱されて以来、何度もブームと停滞期を繰り返しながら、現在の私たちの暮らしに深く浸透するまでに発展してきました。
今では、検索エンジンやスマート家電、ビジネスの自動化ツールなど、あらゆる場面でAIが使われており、その活用は教育分野にも広がっています。
特に英語学習においては、AIによる発音チェックやカリキュラムの最適化など、より効率的で個別に合わせた学習が可能になっています。
今回ご紹介したことを踏まえ、AIの歴史を振り返り、さまざまな分野でAIを上手に活用していきましょう。