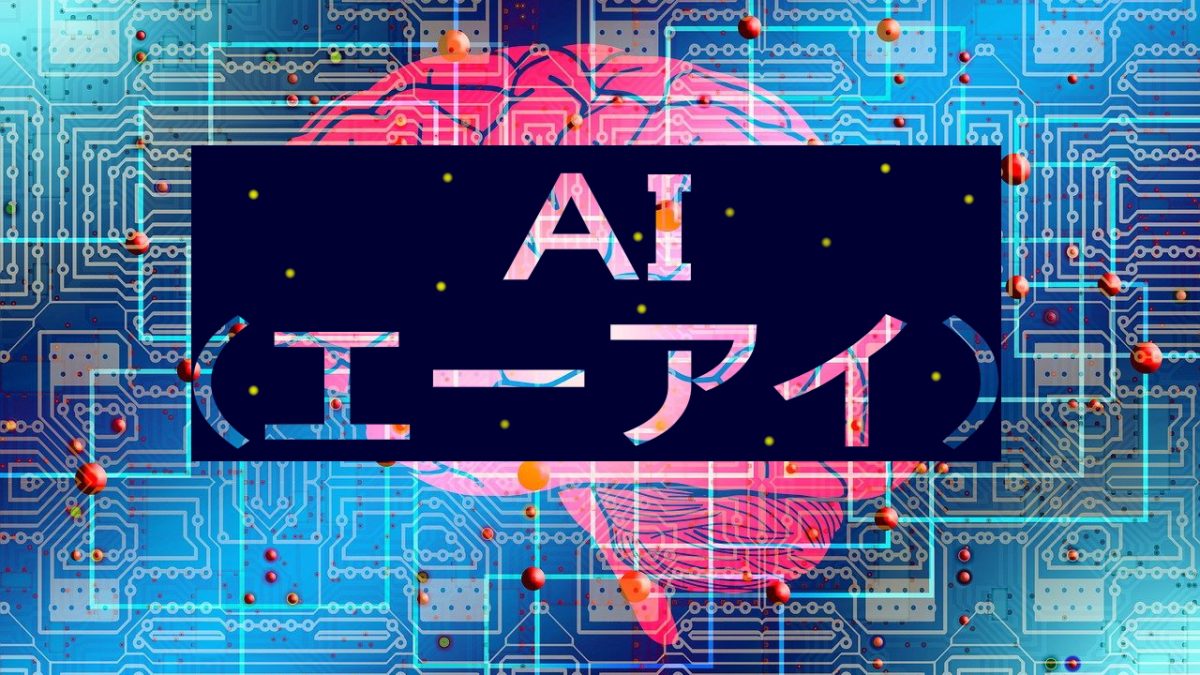みなさんは「AI(エーアイ)」という言葉を聞いたことがありますか?
テレビやニュース、インターネットなどでよく見かけるこの言葉、ちょっとむずかしそうに聞こえるかもしれません。しかし、じつはわたしたちの身のまわりにAIはたくさんあって、毎日知らないうちに使っていることもあります。
この記事では、「AIってなに?」「どんなことに使われているの?」といったギモンに、やさしく答えていきます。
英語を勉強するのにも役立つAIのお話もあるので、ぜひさいごまで読んでみてください!
AI(エーアイ)って何?

AIとは、「人工知能(じんこうちのう)」をあらわす英語です。
かんたんにいうと、「人間のように考えたり、学んだり、判断(はんだん)したりできるコンピューターの頭脳(ずのう)」をあらわしています。
わたしたちは、いつも頭で何かを考えて生きていますね。しかし、すべてを頭で考えるのは大変なので、だれかに代わってもらいたいことも多いでしょう。そんなとき、AIがわたしたち人間のかわりに考えてくれます。
たとえば、
- わからない言葉を調べるときに、検索(けんさく)エンジンがピッタリのページを見つけてくれる
- スマートスピーカーに「今日の天気は?」と聞くと、ちゃんと答えてくれる
- お店のホームページで、チャットのロボットが質問に答えてくれる
これらができるのは、すべてAIのおかげなのです。
AIって何の略?
「AI(エーアイ)」という言葉は、英語の “Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)” の頭文字(かしらもじ)をとったものです。
それぞれの言葉の意味は、こんなふうになっています。
- Artificial(アーティフィシャル)=人工(じんこう)の
- Intelligence(インテリジェンス)=知能(ちのう)(考えたり、おぼえたりする力)
この2つの言葉を合わせて、人工知能は「人間のように考えることができる、つくられた頭脳(ずのう)」の意味になるのです。
AIは何のためにつくられたの?

AI(人工知能)は、「人間の生活をもっと便利(べんり)にするため」に作られました。
たとえば、人間がやると時間がかかる仕事や、まちがえやすい仕事でも、AIならすばやく正確(せいかく)にできます。
そして、AIはたくさんの情報を一度にすることも得意(とくい)なので、人手(ひとで)が足りないところをAIが手伝ってくれると、だれかの負担(ふたん)をへらせます。
だから、工場(こうじょう)やお店、病院(びょういん)や学校など、いろいろな場所でAIが使われています。
AIをつくったのは誰?
AIのはじまりは、今から70年以上も前の1950年代(ねんだい)にさかのぼります。
AIという考え方を最初に出したのは、イギリスのアラン・チューリングさんという科学者(かがくしゃ)です。チューリングさんはある日、「コンピューターも人間のように考えられるのでは?」とひらめき、そこからAIの研究(けんきゅう)が始まりました。
その後、アメリカの大学などでもAIのしくみを研究する人たちがあらわれて、少しずつAIにできることが増えていきました。
最初はかんたんなゲームのようなものしかできなかったAIも、今では会話(かいわ)したり、運転(うんてん)したり、絵をかいたりできるまでに成長しています。
つまり、AIは1人の発明(はつめい)ではなく、世界中の人たちが力を合わせて、少しずつ育ててきたものです。これからも、たくさんの人の力で、AIはもっとかしこくなっていくでしょう。
身近(みぢか)なAIの例は?
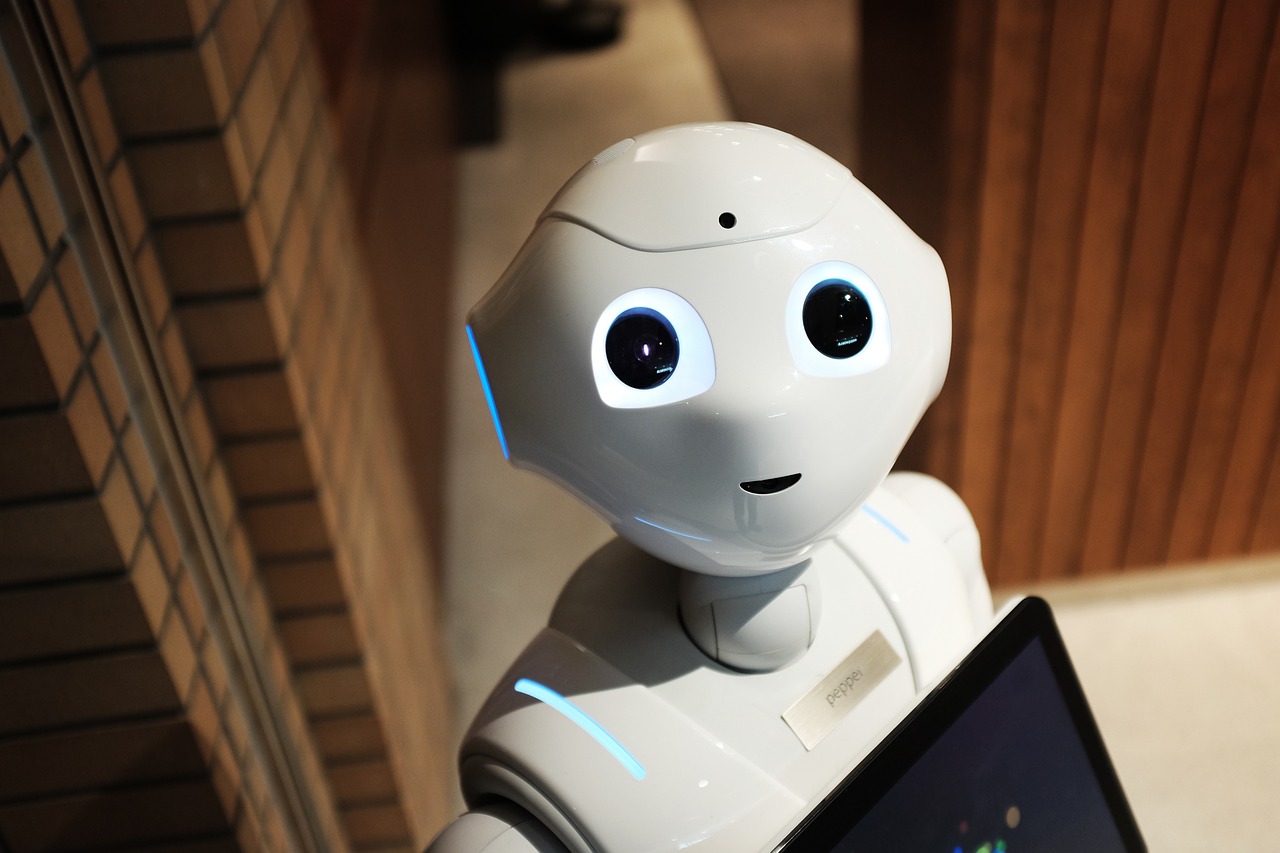
AIは、わたしたちのまわりの、いろいろなところで使われています。
ここでは、毎日の生活の中で出会えるAIの例を見ていきましょう。
インターネットの検索エンジン
わからないことをインターネットで調べるとき、「いちばん合っているページ」を見つけてくれるしくみがあります。
この裏では、AIが言葉の意味を考えて、ぴったりの答えを選んでくれているのです。
スマートフォンの音声アシスタント
スマートフォンやスマートスピーカーに「今日の天気は?」などと話しかけると、答えてくれる機能がありますね。
これには、声を聞きとって、内容を考えて答えるAIが使われています。
チャットボット
お店などのホームページで、「ご質問はありますか?」とメッセージが出てくることがあります。
これにも、AIが人のように会話(かいわ)してくれるチャットボットというしくみが使われています。
車の自動運転やアシスタント機能
自動車にもAIが使われていて、ぶつかりそうになったときにブレーキをかけたり、車線(しゃせん)からはみ出さないようにしたりしてくれます。
さらに、最近では人間がハンドルを操作(そうさ)しなくても、自動で運転できる車の研究も進んでいます。
お掃除ロボット
家の中を動き回ってゴミを吸い取るロボットにも、AIが使われています。
AIが部屋の形をおぼえて、上手にそうじできるように考えたり、ぶつからないように動いたりしています。
エアコン、冷蔵庫、洗濯機
最近の家電(かでん)には、AIが入っているものがたくさんあります。
たとえば、部屋の温度(おんど)に合わせて自動で調整(ちょうせい)するエアコンがあります。そして、カメラで食材(しょくざい)をチェックして、「何があるか」「何が足りないか」を教えてくれる冷蔵庫もあります。
また、服の量やよごれに合わせて水の量や洗い方を変えるAI洗濯機(せんたくき)もあり、むだなく、きれいに洗たくできるようになっています。
AIは英語の勉強にも役立っています!
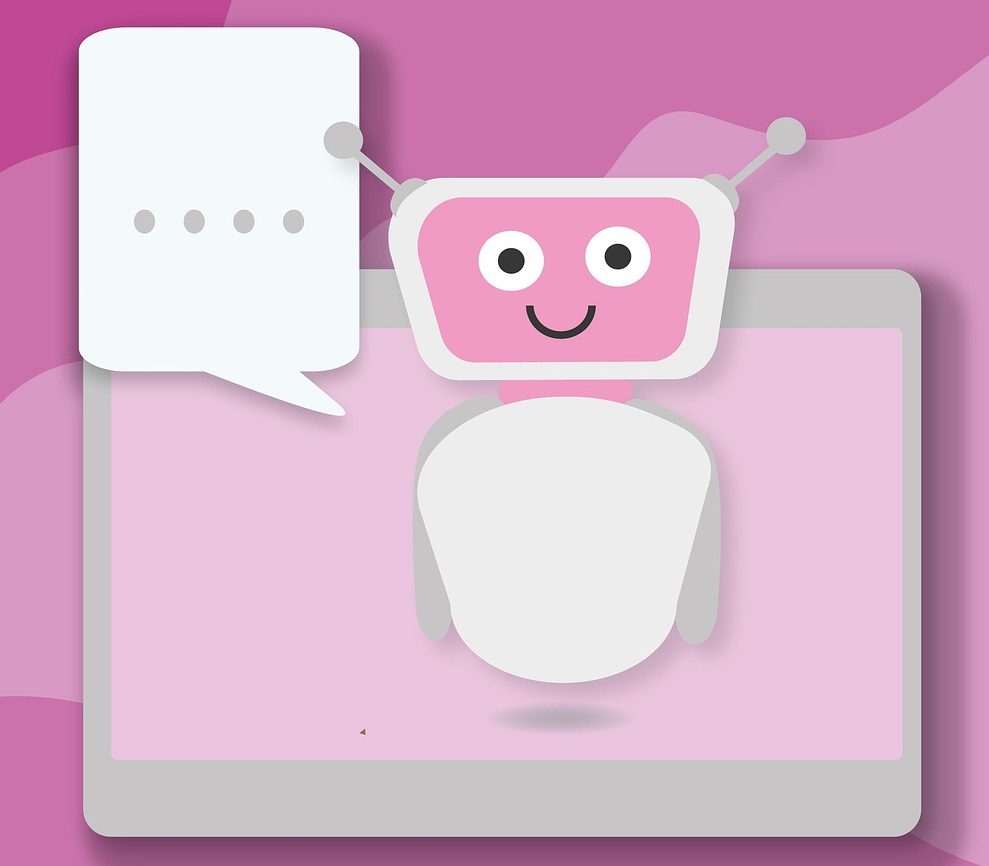
AIは、わたしたちの勉強にも役立ちます。とくに英語を勉強するときは、AIの力で楽しく、わかりやすく学べるようになってきました。
たとえば、AIを使うと次のようなことができます。
- 自分の発音(はつおん)と、ネイティブの発音をくらべてチェックしてくれる
- 英語の文を書いたとき、文法(ぶんぽう)のまちがいを見つけて、なおしてくれる
- その人のレベルや学び方に合った教材(きょうざい)や練習問題を選んでくれる
学研(がっけん)のオンライン英会話「Kimini英会話」では、AIと先生がいっしょに英語を教えてくれるしくみがあります。
小学生向けの、動画やクイズを使った楽しいレッスンもあって、「はじめて英語を学ぶ子」でも、無理なく学べるようになっています。
さらに、スマートフォンのホーム画面にアイコンを追加(ついか)すれば、アプリのようにクリック1つでレッスンに入れる「らくらくログイン」も使えて、とても便利です。
「英語がちょっと苦手…」という人も、きっと自信がついてくるはずなので、ぜひAIを英語の勉強に使ってみましょう!
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
まとめ
この記事では、「AIってなに?」「どんなことに使われているの?」をやさしく紹介してきました。
AIは、人のかわりに考えたり、手伝ったりしてくれるコンピューターの頭脳(ずのう)です。お店や家、学校など、いろいろなところで活やくしていて、英語の勉強にも役立っています。
今回の内容を参考にして、AIといっしょに、できることをもっとふやしていきましょう!