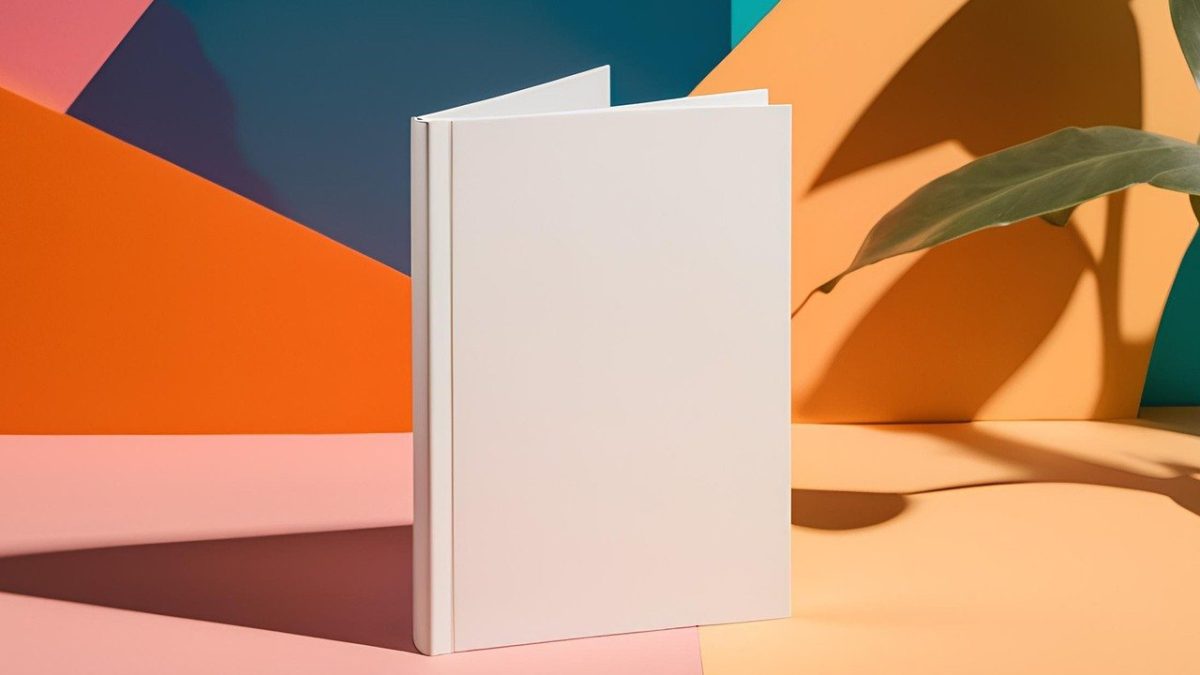文章を読む時間が足りなかったり、大量の資料に目を通すのが大変だったりするときに便利なのが、AI要約です。AI要約を活用すれば、効率的に情報収集でき、学習やビジネスの場面で大いに役立ちます。
この記事では、AI要約の概要やメリット、使ううえでの注意点、おすすめツールなどを詳しく解説します。
記事の後半では、英語学習への活用法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
AI要約とは?
AI要約とは、人工知能(AI)が文章の内容を理解し、重要な情報だけを抽出して短くまとめる技術、およびそれを使ったツールを意味します。
AI要約では、文章全体の構成や意味を把握しながら、人間が書いたような自然な要約文を生成することが可能です。
たとえば、新聞記事や研究論文、ブログなどの長文をAIに読み込ませると、数秒で内容を3行〜5行程度に要約してくれます。もちろん、ニーズに合わせて要約文の長短の調整も可能です。
従来の機械的な抽出型要約とは異なり、近年のAI翻訳では生成AIの技術を応用することにより、文脈を踏まえた自然な要約ができるようになりました。その結果、学習からビジネスまで、多くのシーンで活用の幅が広がっています。
AI要約を使うメリット

AI要約を使うことで、学習からビジネスまで、幅広い場面でメリットが得られます。
ここでは、代表的な3つのメリットについて、詳細を確認していきましょう。
情報収集の効率化
AI要約を使う1つ目のメリットは、情報収集が効率的に行える点です。
ニュース、ビジネスレポート、論文、SNS投稿など、現代は読まなければならない文章がたくさんあります。AI要約を活用すれば、これらすべてに目を通さなくても、要点だけを効率的に把握できます。
たとえば、複数のニュースサイトの記事をAIで要約し、要点だけを比較することで、短時間で全体像を把握できます。
また、学習の際は、教科書や参考書、論文などの長文を要約することで、学習効率を高められます。
書く作業の時間短縮
AI要約を使う2つ目のメリットは、文章を読む時間だけでなく、書く作業の時間も短縮できる点です。
学習の場面では、レポート、感想文、課題提出など、「文章をまとめる作業」が頻繁に求められます。その際、AIに一次的な要約を任せることで、作業を効率よく進められます。
たとえば、授業で扱った長文の資料や参考文献をAIで要約し、その要点をもとに自分の考えを組み立てれば、レポート作成にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。
また、AI要約はビジネスの場面でも役立ちます。会議録や報告書、プレゼン資料などの下書きをAIに任せることで、要点整理や時短につながり、他の業務に充てる時間を確保しやすくなるでしょう。
文章のクオリティ向上
AI要約を使う3つ目のメリットは、文章のクオリティを高められる点です。
自分が書いた文章をAIに要約させることで、「自分が本当に伝えたかったこと」が浮き彫りになり、内容の見直しや改善に役立ちます。たとえば、報告書やプレゼン資料の原稿をAIに要約させると、冗長な表現や論点のズレを見つけやすくなり、読みやすく伝わりやすい文章に仕上げられます。
また、教育現場や学習の場面でも、AIに文章を要約させて要点を把握することで、論理的に構成された文章を書く力が養われます。
AI要約の注意点

AI要約は非常に便利な存在ですが、使用するうえでは注意点もあります。
ここでは、特に覚えておきたい4つの注意点について、順に確認していきましょう。
要約が常に正確とは限らない
AIによる要約は非常に便利ですが、生成される内容が必ずしも正確とは限らない点に注意が必要です。
特に、複雑な文脈や言い回し、比喩表現などを含んだ文章では、AIが意図を誤って解釈してしまうケースがあります。
たとえば、ある記事で「皮肉」を込めた表現があった場合、AIがそれをそのままの意味で受け取り、事実と異なる要約を出力してしまうこともあります。
そのため、AIが作成した要約はあくまで1つの目安として活用し、重要な情報は自分の目で確認するようにしましょう。
長文の要約には対応できないことがある
AI要約ツールは、入力できる文字数やデータ量に制限があり、長文には対応できない場合があります。
たとえば、1万字を超えるような論文や書籍の全文を一度に要約しようとしても、上手く動作しなかったり、不完全な要約になったりします。
このような場合は、章ごとやセクションごとに文章を分割してAIに読み込ませるなどの工夫が必要になります。
また、PDF形式やスキャンされた資料などを扱う場合は、事前にテキスト形式に変換しなければならないことも多いので注意しましょう。
専門的な文章、個人的な文章には弱い
AI要約は、一般的な文章には対応できますが、医学・法律・科学などの専門的な知識を要する文章については、精度が落ちる傾向があります。
たとえば、医療分野の論文をAIで要約した場合、重要な専門用語を誤って解釈したり、省略してしまったりすることがあります。
また、感情や価値観が強く反映された個人的な文章の要約にもまだ弱いです。たとえば、小説やエッセイのような感情表現の多い文章では、文の背景にある意味を上手く拾えないことがあります。
そのため、専門的な文章や個人的な文章を扱う際は、AIの要約を参考程度にとどめ、人間の目での確認と修正を前提に活用することが重要です。
セキュリティに注意が必要
AI要約ツールを使う際は、取り扱う情報のセキュリティにも注意が必要です。
たとえば、業務上の機密情報や個人情報を含む文章をそのままAIに入力するのは、情報漏洩のリスクを伴います。特にクラウドベースのツールでは、入力内容がAIの学習データとして使われる可能性もあるため、利用規約やプライバシーポリシーをしっかり確認しておきましょう。
そのため、AI要約ツールを使う際は、セキュリティ対策が施された信頼できるサービスを利用するようにしましょう。
おすすめのAI要約ツール
AI要約を安心して活用するには、信頼できるツールの選定が重要です。
ここでは、使いやすさや実用性の面で人気のある代表的なツールを2つご紹介します。
ChatGPT
OpenAIが開発したChatGPTは、文章生成に特化した対話型AIで、要約タスクにも対応しています。
使い方はシンプルで、要約したい文章を入力し「要約してください」と指示するだけでOKです。
無料でも利用できますが、有料プランではより高性能なモデル(GPT-4)が使えます。
Copilot
MicrosoftのCopilotは、WordやOutlookなどのOffice製品に統合されたAI機能です。
ドキュメントやメール、PDFの内容を自動で要約してくれるため、日常業務の効率化に役立ちます。
操作はOfficeアプリ内から行えるため、ビジネスユーザーにとって導入のハードルが低い点も魅力です。
要約AIは英語学習にも活用できます

要約AIは、情報整理や時短に役立つだけでなく、英語学習にも応用できる便利なツールです。
たとえば、英語のニュース記事や論文などをAIで要約すれば、英文全体を読み込まなくても要点だけを効率よく把握できます。これにより、英語を読むハードルが下がり、多読の習慣付けにもつながります。
また、学校の課題や英語のエッセイを書く際にも、下書きをAIに要約させて構成を見直すことで、論理的な文章づくりのサポートになるでしょう。
さらに、自分が書いた英文をAIに要約させるという使い方もおすすめです。AIがどう読み取り、どのようにまとめたかを確認することで、伝えたいことが正確に書けているかを客観的にチェックできます。
このように、AI要約は読む・書く・考える力をバランスよく伸ばしたい英語学習者にとって、頼れる学習サポーターになってくれるでしょう。
なお、学研のオンライン英会話「Kimini英会話」では、AIと講師による学習を組み合わせたレッスンを提供しています。AIで要約した英語教材をもとに講師と会話練習を行うなど、効率的かつ実践的な学習が可能です。
さらに、スマートフォンのホーム画面に登録しておけば、アプリのようにワンクリックでアクセスできる「らくらくログイン設定」もご利用いただけます。
スキマ時間に英語を学びたい方、AIを活用して英語力を伸ばしたい方は、ぜひKimini英会話をチェックしてみてください。
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
まとめ
今回は、AI要約とは何かについて、メリットや注意点、おすすめツールなどを詳しく確認してきました。
AI要約は、文章の内容を素早く把握したいときに非常に役立つ便利なツールです。情報収集の効率化、書く作業の時間短縮、文章のクオリティ向上といったメリットがあり、学習やビジネスなど、さまざまな場面で活用できます。
一方で、すべての要約が完璧というわけではなく、長文への対応や専門性の高い文章には限界もあります。また、ツールのセキュリティ面にも注意が必要です。
要約AIは英語学習との相性も良く、英文読解やライティング力の向上にもつながります。ツールの特性を理解し、自分に合った形で上手く取り入れることが重要です。
今回ご紹介したことを参考にして、文章を読む・書く作業をもっとスムーズに進めたい方は、AI要約を日常の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。