皆さんはAIをうまく活用できていますか?
こちらの記事ではAIの活用方法をご紹介していきます。具体的な活用事例から、活用する上での注意点も紹介中です。
AIをうまく使っていくためのノウハウが詰まっているので、ぜひ参考にしてください。
AIの活用方法とは?

私たちの生活やビジネスに急速に浸透しつつあるAI。
その可能性を最大限に引き出すには、どのように取り入れていくべきなのでしょうか。
今回は身の回りでよくある、AIの活用方法とその事例についてご紹介していきます。
AIと共にタスクを効率化する
AIの活用方法としてまずその真髄を理解するのが大事です。
AIの真髄は、私たち人間が苦手としている単調な作業や膨大な情報処理を驚くべきスピードでこなしてくれることにあります。
日々の業務で感じる「この作業、もっと楽にならないかな」という悩みの多くは、AIによって解決できることがほとんどです。
例えば、プレゼン資料の作成に丸一日かかっていたところ、AIを活用したら1時間以内に終わらせることもできます。
情報の網羅性も人間の手作業より高く、驚くほど効率的なのです。
生成AIをビジネスに活かす
生成AIをビジネスに活かすのも、2025年の現在では当たり前になってきました。
「アイデアはあるけど形にする時間がない」といったよくある悩みを抱えるビジネスパーソンにとって、生成AIは心強い味方になります。
文章、画像生成、アイデア出しまで短時間で形にしてくれるのが魅力です。
身近な例でいうと「夜ごはんのアイデアをください」といったような、カジュアルなアイデア出しでも生成AIが役だったりします。
他にも、テーマだけ決めて生成AIに草案を作ってもらい、それを編集するというフローに変えたところ、作業時間が3分の1になったような例もあるようです。
もちろん最終チェックと微調整は人間が行いますが、大幅な時間短縮は間違いありません。
AIに完全委託する
これまではAIとの共生によって、効率的にタスクを進めていく目線でご紹介してきました。
しかし、もちろんAIに完全委託することも可能です。実際、私たちの仕事の中には「これ、機械でもできるよね」という作業がたくさんあります。
データ入力やルーティンワークなど、パターン化された業務はAIに丸投げしてしまうのも一つの選択。
その分、私たち人間は本当にやるべき「創造的な仕事」に集中できるようになります。
つまり、誰もがPMやディレクターになれるようなイメージです。
AIの活用事例|応用分野
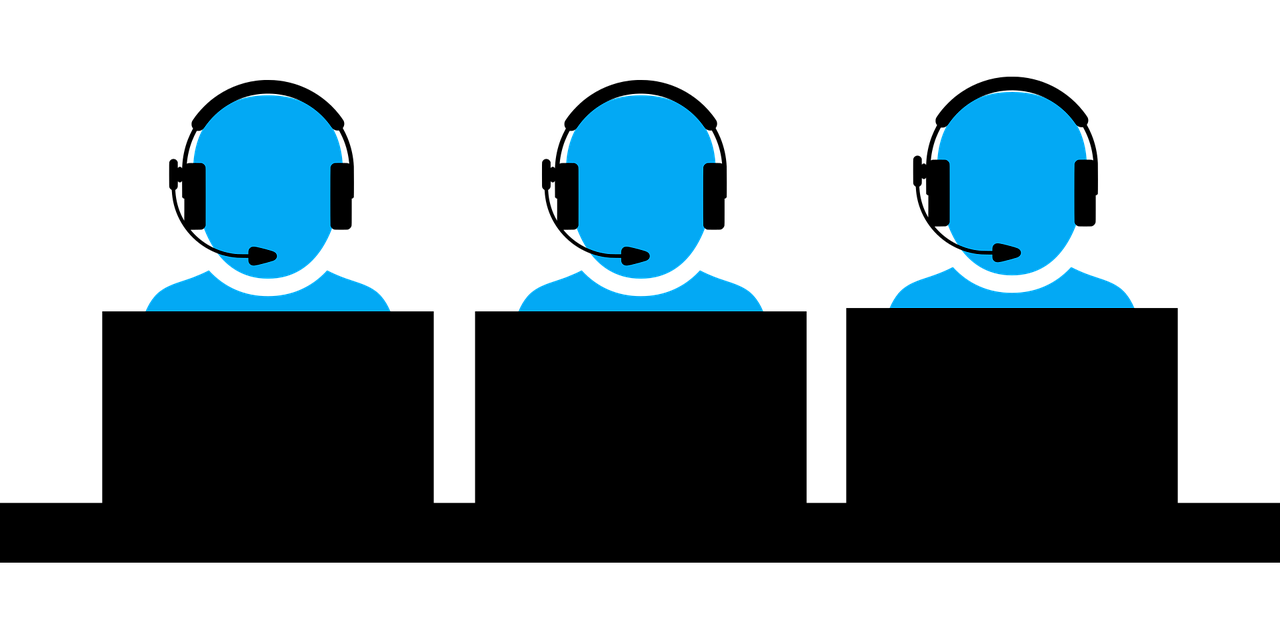
AIは今日、さまざまな分野で当たり前のように使われるようになりました。
AIとの共生から、AIへの完全委託という目線からここからは実際の事例をご紹介していきます。
今回はAIのマルチモーダルを活かして、色々な分野での事例をまとめました。
カスタマーサポートの代行
「お客様からの問い合わせ対応、もっと早くできないかな」という課題を持つ企業は多いはず。
そんな時に、AIチャットボットを導入することで、深夜や休日も含めた24時間サポートが可能になります。
平日5営業日のみで、営業時間外は「対応不可」としていた企業が、AIの力によって深夜でも対応ができるような仕組みができているのです。
また、AIに全て任せるのではなく、一次受けをAIに行ってもらい、よくある回答パターンに当てはまる場合はAIで完結。当てはまらない場合は、人間が引き受けるといった、一部のみサポートをお願いするような企業も多いです。
身近な例でいうと「Uber Eats」のサポートはほとんどがAIによって解決されています。
英語の一次翻訳を依頼する
英語の一次翻訳をAIに依頼するのも、最近流行っている使われ方です。
海外とのやり取りで頭を悩ませる英語メールは、「このニュアンスで伝わるかな?」と不安になることも多いですよね。
実際グローバル化が進んでいく世の中で、海外企業との取引が必要な場面はどの企業でも増えてきました。
従来は「英語が分かる人」に任せていた翻訳部分を、AIによって代行してもらうことが現在では可能なのです。
文法ミスも減り、コミュニケーションがスムーズになるので非常におすすめな活用方法となります。
一次翻訳だけを任せる理由
ちなみに英語の一次翻訳だけを任せる理由としては、AI感がどうしても残ってしまうのが理由です。
最近よく迷惑メールなどでもAIが使われていたりしますが、日本人目線「これ日本語おかしいな」と気が付ける場面が実際あると思います。
まさにあれが課題となっており、だからこそ一次翻訳だけをAIに任せるのがおすすめなのです。
ちなみに単語の整合性チェックはKimini英会話がおすすめです。以下に便利なショートカット登録の方法もご紹介しているので、ぜひこの際に登録しておきましょう!
iPhone/iPadの場合
- Kimini英会話へログイン(アカウント作成必須)
- スマホの「共有ボタン」をタップ
- 「ホーム画面に追加」/「ショートカットを作成」を選ぶ
- スマホホーム画面へショートカットが作成
- 「Kimini英会話」アイコンをタップで簡単アクセスが可能
Androidの場合
- Kimini英会話へログイン(アカウント作成必須)
- 右上の「︙」をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 「インストール」/「ショートカットを作成」を選ぶ
- 「インストール」/「追加」をタップ
- スマホホーム画面へショートカットが作成
- 「Kimini英会話」アイコンをタップで簡単アクセスが可能
スマホのホーム画面へKimini英会話を追加することで、ログイン状態を保ちつつ、いつでも情報を確認することが可能です。
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
アイコンをAI生成してもらう
「デザインを外注すると高いけど、自分ではセンスに自信がない…」そんな悩みも、AI画像生成で解決できるかもしれません。
具体的なイメージを伝えるだけで、複数のデザイン案を提案してくれます。
ただし、著作権周りには要注意です。「自分の作ったここと一致してる」と断定されてしまうと、問題になる可能性があります。
安眠BGMをAI生成する
仕事で疲れた夜、心地よい眠りにつくためのBGMもAIが作ってくれます。
音楽といえば「才能を持った人しか作れない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、音楽生成AIを使えば「こんな感じ」をうまく伝えると、自分好みの音楽を作ってくれるのです。
個人の好みに合わせてカスタマイズできるのが魅力的といえます。
AI活用時の注意点

最後に便利なAIだからこそ、注意すべきポイントも存在します。
ここでは具体的に何に注意すれば良いのか、2つのポイントでまとめました。
著作権に注意する
便利なAIですが、生成されたコンテンツが意図せず他の作品に似てしまうケースがあります。
実際生成AIが原因で、生成物の指し止めや損害賠償を求めることが可能です。
AIがデータを学習すること自体は法律上問題ありませんが、生成AIによって作成された作品が既存の作品と酷似していたり、元の作成者が特定できる特徴を持っていたりする場合は、著作権侵害と見なされることがあります。
特に商用利用をする際などは、注意が必要なのです。
AIに頼り過ぎない
「便利だからすべてAIに任せよう」という考え方は危険かもしれません。
すべてAIに頼るようになると、自分で考えて処理する能力が落ちてしまう可能性があります。
AIはあくまでツール。私たちの思考力や創造性を鍛える機会まで奪われないよう、バランスを考えることが大切です。
まとめ
AIとの付き合い方は、まさに発展途上。
上手に活用すれば、私たちの仕事はより創造的で、生活はより豊かになるでしょう。
大切なのは、AIに使われるのではなく、私たちがAIを使いこなすという姿勢です。
皆さんも、日々の生活やビジネスの中で「この作業、AIに任せられないかな?」と考えてみてはいかがでしょうか。
新たな可能性が見えてくるはずです。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。


