「AIはまだまだ近未来の話」だと感じている人もいるでしょう。しかし、科学技術の発展に伴い、AIや最新テクノロジーが日々の生活の中に入りつつあります。
スマートフォンはもちろん、家電や自動車、医療や教育など、さまざまなところに科学技術が使われているのです。
そこで、今回はAIと科学技術がどれほど身近になっているのか、日常生活の具体例を交えながら見ていきましょう。
SFのような世界が訪れている

SF映画などでは、車が自動で走ったり、ロボットが接客をしたりといったシーンを見たことがあるでしょう。映画を見ているときは、近未来の話であり、フィクションだと思っていた人も多いのではないでしょうか。
しかし、科学技術の発展に伴い、自動運転や話すロボット、空を飛ぶドローンなど、映画の中の世界が現実になっているのです。
中でも、AI(人工知能)の進化は目覚ましく、すでに私たちの暮らしの中で当たり前の存在になりつつあります。
AIは日々の生活にもたくさん使われている
昨今はさまざまなところでAIが使われています。気づかないうちに、AIの力に頼っているケースも少なくありません。たとえば、スマートフォンの顔認証機能、YouTubeやNetflixのおすすめ動画の表示、スマートスピーカーとの会話、カーナビの渋滞回避ルートの提案など、すべてAIによるものです。
つまりAIは、「最新技術」というより「生活の一部」であると認識したほうがいいといえるでしょう。科学技術の発展により、今後もさまざまなところでAIが使われていくと考えられます。
科学技術の身近な例
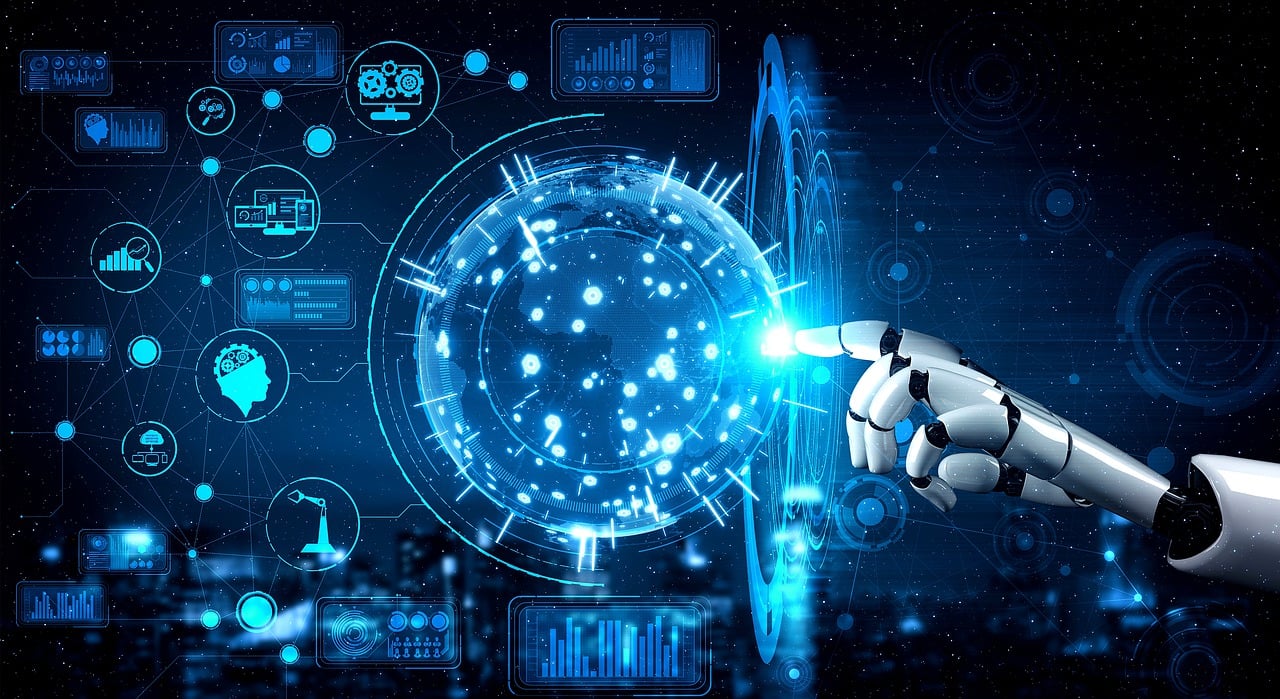
AIや科学技術が発展していくなかで、さまざまなところでAIが使われるというのは理解できたでしょう。しかし、具体的にどういったシーンで科学技術が使われているのか、いまいちイメージできない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、科学技術の身近な例について解説します。
自動運転
車はただの移動手段ではなくなりました。今や、カメラやセンサー、AIが搭載された「スマートカー」が登場し、歩行者や障害物を自動で検知してブレーキをかける機能が備わった自動車が市場に出始めています。完全自動運転までは時間がかかるものの、AIによる「運転支援」はすでに広く普及しているといえるでしょう。
AI家電
ロボット掃除機が部屋の間取りを記憶して効率よく掃除したり、エアコンが室温や人の動きを感知して自動調整したりなど、AI家電も普及してきています。さらに、冷蔵庫の中身をスマホでチェックできたり、AI機能が備わった洗濯機などもあったりします。普段なにげなく使用している家電に、実はAIが搭載されているといったケースも少なくありません。
科学技術の発展とともに、今後はますますAI家電が増えていくでしょう。
医療ロボット
レントゲン画像やCTスキャンの診断補助、がんの早期発見、さらには手術支援ロボットなど、医療業界においても最先端科学技術を用いたAIがたくさん活用されています。AIは医師の“第二の目”として治療をサポートし、診断精度や治療の効率を高めています。
人の命を預かる現場で、AIが信頼される存在になりつつあるのは、大きな進歩といえるでしょう。
教育・英語学習
AIを活用したオンライン学習プラットフォームでは、学習者の理解度に応じて教材が自動で変わるといったサービスが展開されつつあります。「苦手な分野を集中的に練習する」など、AIが家庭教師のような役割を果たすようになってきています。
また、Kimini英会話のように、AIを活用したスピーキングテストなどもあります。最先端テクノロジーを駆使したAIシステムにより、語彙力やリスニング能力などを数値やグラフにして教えてくれます。
また、Kimini英会話は、アプリのようにワンクリックでウェブサイトにログインができる「らくらくログイン設定」というサービスも提供しているのが特徴です。スマートフォンやタブレットのホーム画面にショートカットを作成しておけば、アプリのようにワンクリックするだけでログインすることができ、気軽に利用できるのが魅力的です。
iPhone/iPadの場合
- Kimini英会話へログイン(アカウント作成必須)
- スマホの「共有ボタン」をタップ
- 「ホーム画面に追加」/「ショートカットを作成」を選ぶ
- スマホホーム画面へショートカットが作成
- 「Kimini英会話」アイコンをタップで簡単アクセスが可能
Androidの場合
- Kimini英会話へログイン(アカウント作成必須)
- 右上の「︙」をタップ
- 「ホーム画面に追加」を選択
- 「インストール」/「ショートカットを作成」を選ぶ
- 「インストール」/「追加」をタップ
- スマホホーム画面へショートカットが作成
- 「Kimini英会話」アイコンをタップで簡単アクセスが可能
スマホのホーム画面へKimini英会話を追加することで、ログイン状態を保ちつつ、いつでも情報を確認することが可能です。
アプリのようにワンクリックでログイン可能に!らくらくログイン設定のご案内
防犯・災害対策
駅や空港の監視カメラにAIが搭載され、不審な動きをリアルタイムで検知したり、災害発生時にドローンとAIで被害状況を迅速に把握したりなど、防犯・災害対策の分野でもAIは活用されています。
AI・科学技術が身近になった理由は?
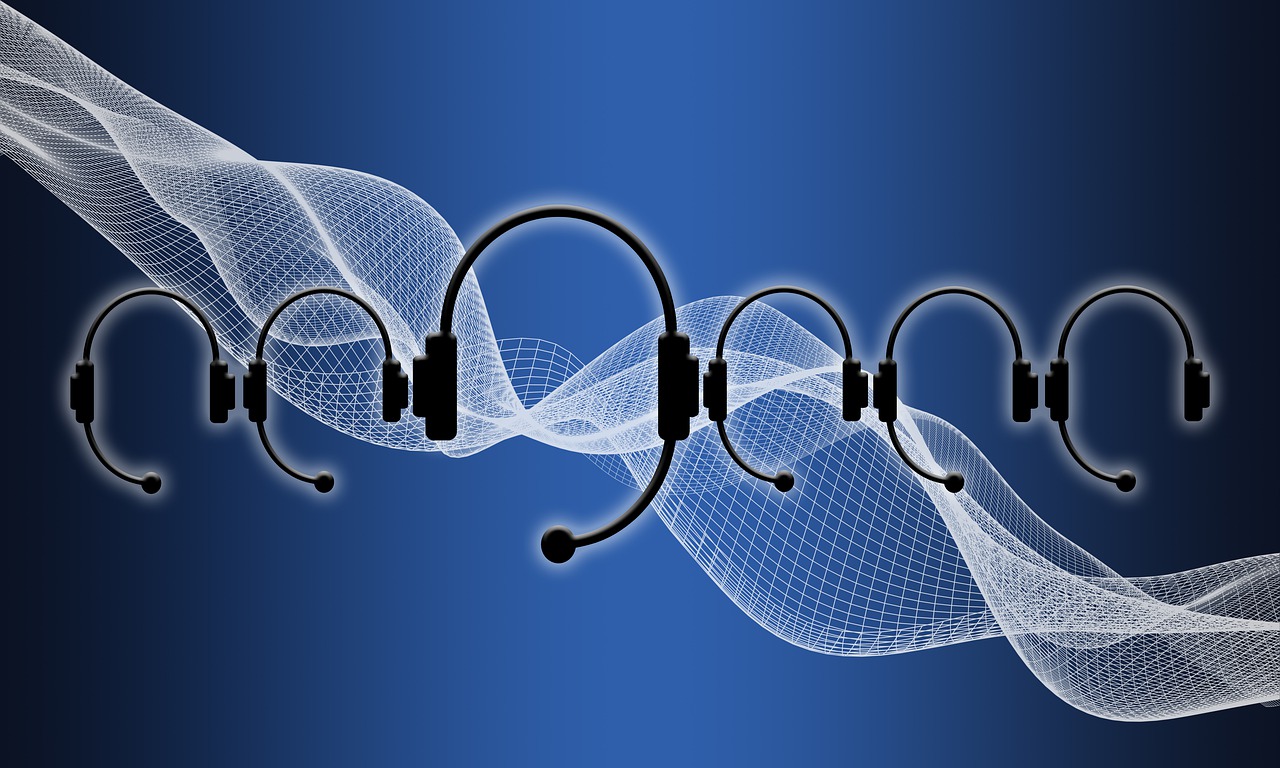
AIが身近になった理由として挙げられるのは、「スマホの普及」「クラウド技術の発展」「社会的ニーズの増加」です。こういった背景と科学技術の発展により、AIが身近な存在となりました。
もともと、携帯電話というのは外出先でも電話ができるといったものでした。しかし、今ではスマートフォンを使って、動画を見たり、編集したり、オンライン会議ができたりなど、日々の生活の中で必要不可欠な存在になっているといえるでしょう。
また、クラウド技術が発展したことにより、データ共有が容易になりました。昔はUSBメモリやCD-ROMなどの物理的な記憶媒体を使って保存やデータ共有をしていましたが、今ではクラウド上でデータのやり取りが可能です。
そのほか、社会的ニーズが高まっている背景があることもAI・科学技術が身近になった理由として挙げられます。日本は人口減少が進んでおり、一部の業界では人手不足が懸念されています。その状況の中で、AIやロボットを使った働き方が主流になりつつあります。
たとえば、これまで有人対応だったレジを無人レジに変更したり、倉庫でのピッキングや検品作業をロボットが行ったりなど、人口減少に対応するためにAIやロボットが活用されているのです。そのほか、コールセンターの自動応答システムや、チャットボットなどもAI・科学技術の発展によるものです。
まとめ
AIや科学技術の進化に対して、不安を感じる人もいるかもしれません。「仕事が奪われる」「人間らしさが失われる」といった懸念を抱いている人も多いでしょう。
しかし、AIとどのようにかかわるかが重要なのです。AIはあくまで「道具」「手段」のひとつであり、決して「脅威」ではありません。AIを使いこなせば、生活や仕事がより豊かになるでしょう。
科学技術は遠い未来の話ではなく、今の時代の話です。そのため、「知らないうちに置いていかれる」のではなく、「自分で選んで取り入れる」ことが、これからの時代を生きる上での大きな武器になるといえるでしょう。


