ヨーロッパの子どもの絵本は、どことなく色合いがシックで、大人でもインテリアに使いたいような味わいがあると思いませんか?
シンプルでわかりやすい点では、アメリカのエリック・カールと比較してしまいがちですが、レオ・レオニには彼独特の世界観があります。
大人も子どもも楽しめる、レオ・レオニの世界をのぞいてみましょう!
1.レオ・レオニの生い立ちと遍歴
レオ・レオニは1910年5月5日、オランダはアムステルダムで、ユダヤ系の裕福な家庭に生まれました。
父親はダイヤモンド技工士で、のちに公認会計士となったルイス・レオニ、母親はオペラ歌手として活躍したエリザベト・レオニです。
アート好きだった叔父たちの影響で、ピカソやクレーなどの芸術品に囲まれて少年時代を送りました。
学生時代は、ベルギーのブリュッセル、アメリカのフィラデルフィアなどの引っ越しを経て、14歳の時にイタリアのジェノヴァに移住し、スイスの大学で経済学を学びました。
1931年21歳の時に当時18歳の妻、ノーラ・マッフィーと結婚し、絵画やデッサンの制作を続けていましたが、ファシスト政権の弾圧を受け、ユダヤ人であってレオはアメリカに亡命します。
アメリカのフィラデルフィアの広告代理店に勤めたのち、ニューヨークに移住し、そこでアートディレクター、グラフィックデザイナーとして成功をおさめます。
1945年にアメリカ国籍を取得し、1953年にはアスペン国際デザイン会議の初代会長を務めました。
そして、そこであのエリック・カールの才能を見出し、エリックにニューヨーク・タイムズのグラフィック・デザイナーの就職を世話して、絵本製作の仕事も勧めたこともありました。
1959年、孫のために作ったという「あおくんときいろちゃん」(原題:Little Blue and Little Yellow)を発表したのがレオの絵本作家としてのデビューになりました。
その後1969年、イタリアトスカーナ州に引っ越したレオは、自身の本のイラスト制作や彫刻の活動を精力的に続け、やがて発表した絵本は約40冊になりました。
1970年代になると、ふとしたことから「架空の植物群」と呼ばれる「平行植物」に魅せられ、研究や構想を積み上げたのち、1976年に学術書「平行植物」を発表し、一躍有名になりました。
そして1999年10月、享年90歳のときにイタリアのトスカーナで、家族に見守られながら亡くなりました。
2.レオ・レオニの作品の特徴

レオ・レオニの作品は、わかりやすく優しい味わいがあります。
彼のアートの特徴は、作品の雰囲気に合わせて、さまざまな技法を使って絵本を作っているところにあります。
作品別に、絵本に使われた技法を見てみましょう。
フレデリック
コラージュ(紙を切って貼り付け絵を完成させる技法)を使い、ネズミの毛は指でちぎって、毛のふさふさした質感を表現しています。
周りの風景の葉っぱや岩などははさみでカットし、シャープさを出しています。
おいうえおのき
スタンピング(かたどったいろいろなものに絵の具や塗料を付けて、紙にポンポンと押して模様を写す技法)が使われていて、木にさわさわと揺らぐ葉っぱを画面いっぱいに描いています。
このアート技法は、幼稚園や保育園でも盛んにおこなわれていますね!
スイミー
モノタイプ(ガラスやアクリル、金属などの板に、油絵の具などの絵画材を用いて絵を描き、その上に紙をのせてバレンなどで圧力をかけて刷り取る技法)というものですが、この技法の「モノ」という言葉はギリシャ語で「ただ一つの」という意味を持っているように、二度と同じものが出来ない、偶然の重なり合いからできています。
スイミーが冒険する水の中や、岩などに多くモノタイプが使われて、この物語独特の温かさが表現されています。
ひとあしひとあし
フロッタージュ(でこぼこした素材の上に薄手の紙をのせ、鉛筆や色鉛筆ででこぼこの模様をこすり出す技法)はフランス語で「Frotter(こする)」を意味しています。
製作者の意図していない絵柄が出てきたりする面白さが、作品にもあふれています。
レオ・レオニの絵本はこのように、いろんな技法を使ってその作品ならではの特徴を出しているためか、アートの世界では「スイミー技法」や「フレデリック技法」と呼ばれることもあり、世界中の子どもたちもその技法を真似て、オリジナルの絵をたくさん描いています。
3.レオ・レオニの代表作品
- 「あおくんときいろちゃん」(Litte Blue and Little Yellow)-1959
- 「ひとあしひとあし」(Inch by Inch)-1960
- 「スイミー」(Swimmy)-1963
- 「フレデリック」(Frederick)-1967
- 「さかなはさかな」(Fish is Fish)-1970
- 「じぶんだけのいろ」(A Color Of His Own)-1975
- 「ペツェッティーノ」(Pezzettino)-1975
- 「ねずみのつきめくり」(Fur katzen streng verbten)-1981
- 「えいごであそぼうよ」(Letters/Words)-1985
- 「ぼくのだ!わたしのよ!ー3びきのけんかずきの かえるのはなし」(It’s Mine!)-1985
- 「びっくり たまごー3びきのかえるとへんなにわとりのはなし」(An Extraordinary Egg)-1994
などがあり、特に「スイミー」は谷川俊太郎氏の翻訳により、1977年から日本の小学校の国語の教科書に採用されたので、私たちには馴染みの深い作品であると言えるでしょう。
最近では、本の感想や評価をチェックしたりweb上やアプリで本棚を作成したりできるサービスがあり、「ブクログ」や「読書メーター」が有名ですが、どれを読むか迷ったら、そういったサービスで「レオ・レオニのおすすめランキング」をチェックしてみるのもいいでしょう。
「読書メーター」では感想欄に本のあらすじを書く人もいて、本を読む前にあらすじを読みたくない人もいるので、あらすじが書いてある場合には「ネタバレ」のマークが入っていてすぐに目に付かないようになっています。
「スイミー」以外にも、「フレデリック」「あおくんときいろちゃん」などが人気があることが分かります。子どもの読み聞かせ絵本として、レオ・レオニの絵本を活用している人がとても多いことにも気付きます。
「フレデリック」のねずみのイラストはどこかで見かけて知っている人が多いですが、そのストーリーを知らない人も意外とたくさんおられるのではないでしょうか。子ども向けの絵本のストーリーには、何かしら人生の教訓が含まれているものです。その人生の教訓をどう捉えるかは、人によって捉え方が違ってくるでしょう。「フレデリック」の絵本を読んでみて、この絵本の作者は読者に何を伝えたかったのかも考えてみるといいですね。
レオ・レオニの絵本作品の魅力は、絵本のエンディングの後のストーリーを自分たちで作れることにもあります。子どもに絵本の読み聞かせをして、エンディングの後のストーリーを考えてもらい、その考えたストーリーを話してもらうと、想像力、思考力を養うことにつながるでしょう。しばらく時間が経ってからまた同じ絵本の読み聞かせをして、エンディングの後のストーリーを作ってもらうと、成長に合わせて考え方が変わりやすい年齢ですから、前回とは違ったストーリーが出てくるかもしれません。
4.レオ・レオニの受賞歴
![]()
- ドイツ児童図書賞・・・「スイミー」
- 児童図書スプリングフェスティバル賞・・・「せかいいちおおきなうち」
- アメリカ図書館協会最優秀作品・・・「チコときんいろのつばさ」
そのほかにも多数受賞しています。
5.谷川俊太郎とレオ・レオニ
レオ・レオニの絵本のほぼすべての日本語翻訳を、谷川俊太郎氏が手掛けていることは、よく知られています。
日本を代表する絵本作家であり詩人の谷川俊太郎氏は、こんな言葉を残しています。
私は絵本にまず美しさを求めます。
絵本を通して子どもたちに何かを伝えたい、そういう気持ちで創られた絵本は多いと思いますが、
私はどちらかというと、ノーベル賞を受けた詩人、T.S.エリオットの「詩は思想をバラの花の香りのように感じさせるもの」という言葉を理想として詩を書き、絵本のテキストを書いています。
メッセージやテーマも大切かもしれませんが、私は絵本にまず美しさを求めます。
絵の美しさ、日本語の美しさ、何を美しいと思うかは個々の絵本によって違いますが、感じ方は読む人、見る人の自由です。
そこに子どもおとなの別はないと思います。
谷川俊太郎
谷川さんはきっと、レオ・レオニの絵の美しさに惹かれ、たくさんの翻訳をされたのでしょうね。
シンプルでリズミカルな谷川さんの翻訳も、心にすっと入ってきます。
英語版と日本語版、両方読んでみると、その気持ちがわかるかもしれません。
2024年11月13日、谷川俊太郎さんが92歳で永眠されました。谷川さんは詩人としても有名ですが、レオ・レオニの絵本の翻訳でもよく知られています。「スイミー」など翻訳本を改めて読んでみたり、子どもに読み聞かせをしてあげたりするのも素敵ですね。
6.レオ・レオニの絵本を原書で読む
1977年から日本の小学校の国語の教科書に採用された谷川俊太郎さんの翻訳本「スイミー」の話をしましたが、レオ・レオニの絵本は、英語で書かれています。
長年、英語を学ばれている皆さんなら読んで意味が分かるようなシンプルな英語です。どんな感じなのか、「スイミー」の冒頭部分を引用して紹介します。
A happy school of little fish lived in a corner of the sea somewhere. They were all red. Only one of them was as black as a mussel shell.
谷川さんの翻訳「スイミー」では、この冒頭部分がこう訳されています。
広い海のなかで、小さな赤い魚の兄弟達が楽しく暮らしていました。でも、そのなかに一匹だけ黒い魚がいました。
絵本の翻訳というのは子ども向けですから、「シンプルに分かりやすく訳す」というのが基本なので、直訳ではなく子どもにも分かりやすい翻訳になっていますね。
原文に出てくるmussel shellというのは、「ムール貝」のことですが、日本ではあまり馴染みがないですし、黒いものの例えとして用いられることがないので、「ムール貝のように黒い魚がいました」としなかったのでしょう。
レオ・レオニの有名な代表作の書き出し部分を、原書と翻訳本で比較してみましたが、原書と読み比べてみると、翻訳でどんな工夫や苦労をされたのかが分かるでしょう。
「スイミー」の翻訳本には、「小さなかしこいさかなのはなし」という副題をついています。実際にこの絵本を読んでみると、まさにその副題どおりの話だと感じるでしょう。
他にもレオ・レオニの代表作が上記に挙げられていますので、面白そうだなと思った本があれば、ぜひ原書と翻訳本で目を通してみてはいかがでしょうか。
7.レオ・レオニの名言
レオ・レオニの作品の中の言葉は、時として哲学的ともいえる、深い意味を含んだ名言があります。
スイミー
「ぼくが、目になろう」
フレデリック
「さむくてくらい ふゆのひのために、ぼくは おひさまのひかりをあつめてるんだ」
「おどろいたなあ、フレデリック!きみって しじんじゃないか!」
ペツェッティーノ
「もしもし、ぼくは きみの ぶぶんひんじゃ ないでしょうか?」
「やっと ペツェッティーノにも わかった。じぶんも みんなと おなじように ぶぶんひんが あつまって できていると。」
あおくんときいろちゃん
「ないて ないて なきました。ふたりはぜんぶ なみだになって しまいました。」
レオ・レオニの絵本をお持ちなら、読み返してみると、新しい発見があるに違いありません!
ここでご紹介しているレオ・レオニの名言は、彼の作品(翻訳)の中の言葉から引用していますが、原書ではその名言がどういう表現だったのかも気になるところですね、
8.スイミーに込められたもう一つの意味とは?
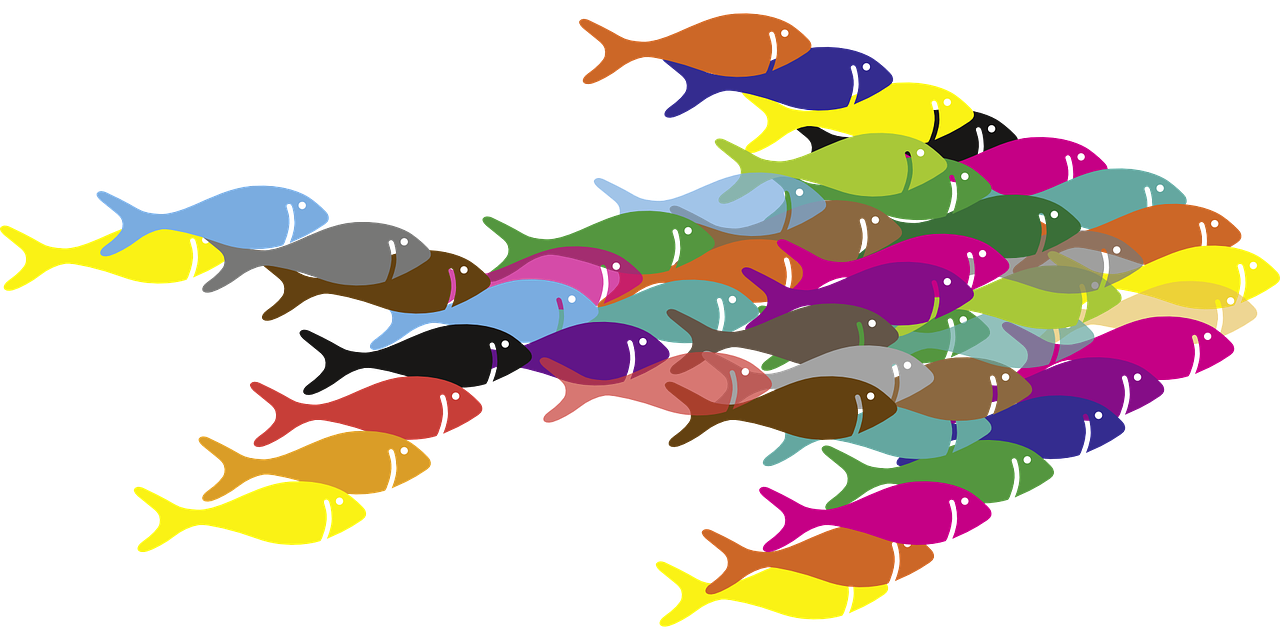
有名な小さなスイミーが、兄弟を失い孤独だった中で、仲間を助け、仲間と協力して大きな魚に立ち向かっていく勇気と知恵を身に着けました。
ユダヤ系ということで、ファシスト政権による人種差別を恐れてイタリアからアメリカに亡命し、戦後もう一度イタリアへ戻ってこの作品を作ったレオは、自分の人生をスイミーに重ね、困難に負けずに生きていくことを意味していたのではないか?
彼の哲学がここにあったと言われます。
レオは晩年、パーキンソン病に侵され、動くことも不自由でしたが、それに負けず、明るい前向きに生きることを絵本に描き、子ども達、また心を病んでいる大人たちへのメッセージにしたのでした。
まとめ
筆者の絵本のコレクションで、エリック・カールとレオ・レオニがかなりの割合を占めていることに、あらためて気づかされるほど、身近にある絵本と言えます。
それは、赤ちゃんから大人までが、いつ何歳で読んでも楽しく、懐かしさを覚え、そして感動も与えてくれるからなのでしょう。幼児のころに読んた絵本は、大人になっても忘れ難く、その時の感動がよみがえってくるので、宝物になる人が多いのではないでしょうか。
スマートフォンの普及もあり、ますます読書離れが進んでいると言われていますが、幼児のころにレオ・レオニやエリック・カールの絵本の読み聞かせをしてあげると、読書の楽しさを知ることができて、大人になっても難なく読書ができるようになるのではと思います。
誰かが「イラストレーターが絵本作家になったら最強」と言っていましたが、絵を描くように、いえ、絵を描くとともに言葉があふれてくるからかもしれません。
絵本は子どもだけのものではなくて、日常に疲れ、難しい言葉で飾り立てて、真実が見えていないこともある私たち大人が読むべき、「絵で聞き、言葉で見る」ようなそんな一冊がレオ・レオニではないでしょうか?


