「フォニックス」は昨今では当たり前のように英語学習に取り入れられていますが、1990年代までは、「フォニックスってなあに?」という程度の物でした。
しかし、最近はフォニックスの重要さが多く叫ばれて、英会話スクールなどでも導入され、教本なども多数販売されています。
英語の学習にフォニックスはどんな効果があるのでしょうか??
1.フォニックスとは?
フォニックスは簡単に言うと、「英語の綴りと音の持つ法則を学ぶことで読み書きを覚える学習法」です。
日本の子供たちが「あいうえお」の50音を覚えるように、欧米の子供たちはフォニックスを学びます。
アルファベット毎の発音を先に学ぶことで、知らない単語でも耳で聞いただけでスペリングがわかり、正しく書くことができるようになります。
訳)簡単に言うと、フォニックスはスペルと発音を結びつけるルールのことです。
訳)フォニックスを学ぶメリットは何ですか?
訳)フォニックスを学ぶ主なメリットは、知らない単語の発音を聞いたときに、そのスペルが推測できるようになることです。
訳)なるほど。発音とスペルの間に関係性があるのは知らなかったです。
訳)もちろん、そのルールには例外がありますよ。ご存知のように、例外のないルールはないですから。
2.フォニックスの歴史
フォニックスの歴史は18世紀にさかのぼります。
当時はほとんどラテン語で聖書を読んでいたのですが、それがやがて英語へと変化していきます。
しかし、最初はなかなかうまく読むことが出来ませんでした。
そこで、それまでのホールランゲージ法(物語を読み聞かせて単語全体をひと固まりとして覚える方法)から、子供にもわかるようによりシンプルに音声と文字の関連性を教えるためにできたのがフォニックスです。
この方法は数々の研究を重ね、1990年ごろから子どもが読み方を覚えるのに効果的だということで英語圏に広まってきました。
日本では、1979年に、松香洋子(松香洋子)さんがフォニックス教育の第一人者としてフォニックスを取り入れ、「松香フォニックス研究所」を作りました。
その後少しずつ広まり始めて、現在では英会話教室でも取り入れているところが多くあります。
3.フォニックスの特徴
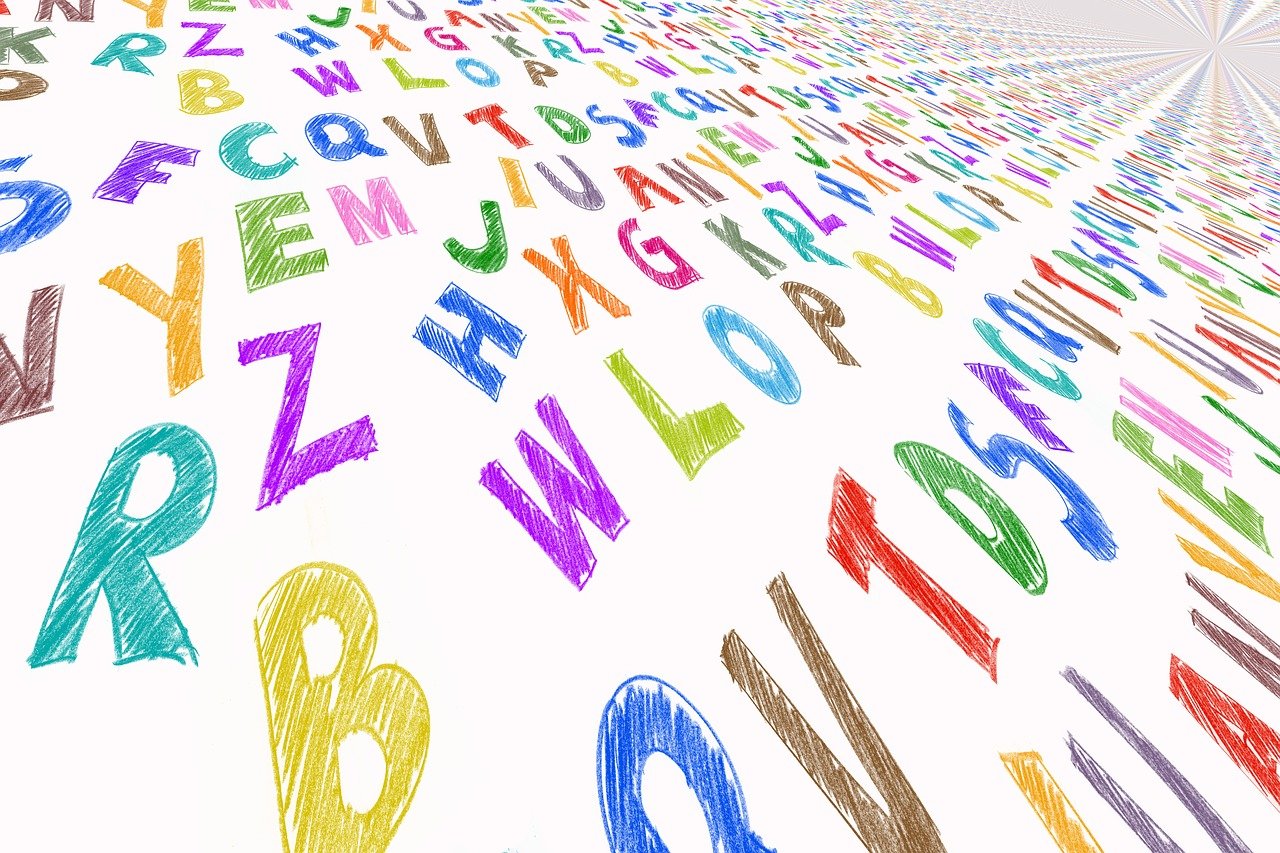
私たちはつい英単語をローマ字読みしてしまいがちですが、実際英語の発音は違います。
例えば、aだと、「エー」、bは「ビー」と読みますが、発音となると、aは「ア」、bは「ブッ」となります。
このように、それぞれの文字(アルファベット)には音があるというのがきまりであり、それぞれの文字に対しての発音を覚えるのがフォニックスの特徴になります。
4.フォニックスの学習法
まず、基礎のアルファベットの文字の発音を練習していきます。
フォニックスは「読み書きのルール」です。
a~zまでの文字には、アルファベット読みと音読みの2通りの読み方があります。
- aーア
- bーブ
- cーク
- dードゥ
- eーエ
- fーフッ
- gーグ
- hーハ
- iーイ
- jージュ
- kーク
- lール
- mーム
- nーン
- oーオ
- pープ
- qークゥ
- rーゥル
- sース
- tートゥ
- uーア
- vーヴ
- wーゥヮ
- xークス
- yーィヤ
- zーズ
これが基本の読み方になります。
例えば、
dードゥ、o-オ、g-グ を組み合わせると d+o+g=ドゥ+オ+グ なので、文字をくっつけて早く言ってみると、ドゥ、オ、グ… ドッグ!
dogは「ドッグ」と発音し、読むことが出来るのです。
- c-ク + a-ア + t-トゥ = c+a+t= ク+ア+トゥ =キャット cat
- d-ドゥ + a-ア +dードゥ = d + a +d = ドゥ+ア+ドゥ = ダッド dad
これが基本のフォニックスの読み方になりますが、他にもたくさんのルールがあります。
5.フォニックスの効果

フォニックスの効果はどんなものか考えてみましょう。
初めて見た単語でも正しく発音できる
フォニックスのルールに従って習得をすることで、初めて見た単語も発音できるようになります。
このルールは、アルファベット24文字を42の音で表すということで、これを把握することで英単語の読み方がわかるのです。
このことで、いちいち辞書なので読み方を調べなくても、すぐに読めるので学習の効率が期待できます。
耳で聞いた英単語を正しくスペリングできる
フォニックスは耳で聞いた初めての単語でも、どんなスペルなのかを推測することが出来ます。
ルールに従い学習していると、音と文字の関連性がわかっているため、英語の音声を聞いただけで単語を文に起こすことも可能になっていきます。
スペル・発音・意味を同時に理解できる
フォニックスを学習すると正しい発音も同時に身についてきます。
スペルや意味なども理解をしたうえで発音の練習を繰り返したら、ネイティヴ並みの発音を手に入れることも不可能ではないでしょう。
リスニング力が向上する
フォニックスで自分で発音できるようになると、必然的に聞き取りが出来るようになります。
発音できる単語が増えれば、リスニングで聞き取れる単語が増えていき、結果正しく聞き取る力が向上します。
6.フォニックスのデメリットは?
このように、良いことばかりのように思えるフォニックスですが、デメリットはあるのでしょうか?
フォニックスのルールは100%ではない
母音(a, i, u, e ,o)や、c, g, s, x, y には基本の26音以外にも読み方があり、また2文字組み合わせると音が変わるなどの特別な組み合わせも発音があるので、例外として暗記するしかありません。
フォニックスばかりだと飽きてしまう
文字や音ばかりにとらわれて、繰り返してばかりの学習だと、子どもであればすぐに飽きてしまう恐れがあります。
7.フォニックスは大人にも効果はあるか?
フォニックスというと「子供」のイメージがあり、また子供のころに身につけるほうが良いと言われていますね。
では、大人には効果はないのでしょうか?
フォニックスを知らずに育った大人世代が、英語を学習してつまずく問題として「カタカナ英語になってしまう」というのは多かれ少なかれあると思います。
フォニックスは大人の発音矯正にも効果があると言われています。
正しい発音が身につけ自分の英語力もアップして、アウトプットしたくなり、会話力も向上するかもしれませんね。
8.フォニックスの種類
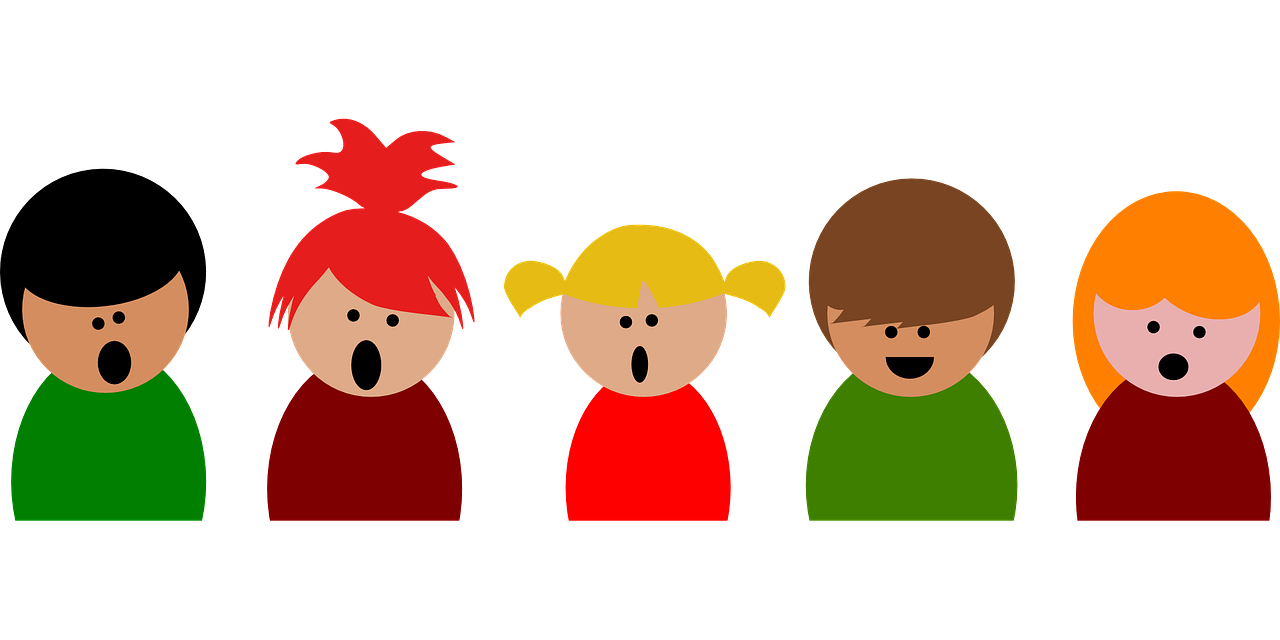
実は、フォニックスには2種類あるのをご存じでしょうか?
一つはアナリティック・フォニックスといい、もう一つはシンセティック・フォニックスと言います。
この二つはどう違うのでしょうか?
アナリティック・フォニックス
こちらのフォニックスはわりと日本でもメジャーと言ってよいでしょう。
1980年代後半から普及し、主にアメリカで主流になっているフォニックスです。
これは、「すでに知っている単語を分解・分析してスペルのルールを知る」というやり方になります。
例えば、aは「ア」の音を学ぶときに ” a says ア, ア, apple.” “ア、ア、ant” ” ア、ア、angry.”といったように aのつく単語を並べて、音のパターンを認識していきます。
単語から文字と音の関連性を分析(アナリティック)していくことが特徴になります。
知らない単語なども読めるようになるメリットは言うまでもありませんが、欠点もあり、ある程度単語を知っている、語彙力があることが前提になるので、まったくアルファベットから始める、となるととても大変であると思われます。
シンセティック・フォニックス
シンセティック・フォニックス1990年代後半から普及し、こちらはイギリスが主流となっています。
シンセティックとは「くっつける」という意味があり、個々の文字の音を組み合わせる学習法です。
このメソッドを使った代表的なものが、イギリス発の “Jolly phonics” です。
これは、ABC順ではなく、よく使われるs, a, tなどから学んでいき、組み合わせて単語にするといった仕組みになっています。
例えばsは /s/ ス)、aは /a/(ア)、tは/t/(トゥ)と発音と文字を確認し、それをくっつけてsat (スアトゥ)→「サット」と読む、といった法則です。
これは、42個の基本の音があり、文字の形、書き方、読み方、基本的な文法を学ぶまでのステージがあります。
英語学習初心者でも安心して取り組める学習法と言えます。
しかしながら、「発音はできても単語の意味が分からない」というデメリットもあると言われています。
9.日本におけるフォニックス
単語を読めるようになる、発音が良くなる、といった意味でも「ではフォニックスをできるだけ多く、早い時期でやったほういいのではないか?」と思われた方もいるでしょう。
しかしながら、ふだんから英語で生活をしているわけでない日本で、あまりにフォニックスばかりにフォーカスしてしまうと、英語学習が単調になり、発音学習に拒否反応を起こすのではないか、という見解もあります。
ですので、リスニングや絵本の読み聞かせ、スピーキングに慣れてから導入させるべき、という考え方です。
フォニックスのインプットだけを教え込むことが目的にならないように、フォニックスはあくまでも「読み書きのツール」としてとらえて、正しい発音をする練習というトレーニングに使うほうが効果的だという専門家も多いようです。
そういった見解もありますが、最初に紹介したように、スペルと発音のルールが分かるようになると、知らない単語の発音を聞いたときに、そのスペルが推測できるというメリットはあります。フォニックス学習を採り入れるかどうかは、そのメリットをどれだけ重要視するかということにもなってきます。
10. アメリカにおけるフォニックス
プリスクール前(0~3歳)
アメリカでは、プリスクールに通う前に、家庭でアルファベットの学習をさせるのが一般的です。まずは、アルファベットに慣れ親しむことから始めていきます。
日本でも、ひらがなの50音字を幼稚園に行く前に、家庭で教えるのが一般的ですね。
プリスクール(3~5歳)
アメリカでは、プリスクール(3~5歳)(日本でいうところの幼稚園)に入学すると、フォニックスの学習が始まります。
アルファベットと単語の中でのその発音を、歌に合わせて覚えていきます。
A is for a a apple, B is for b, b, ball, C is for c, c, cookie, D is for d, d, daddy, E is for e, e, elbow, …といった具合に、歌を歌いながら、アルファベットとその発音をしっかり頭の中にインプットしていきます。
日本の場合、あいうえおの50音表で、「ひらがな」を覚えていきますが、ひらがなの50音は単語や文中でもそのままの音で発音しますが、英語の場合は、アルファベットと単語の中での発音が違うので、フォニックスの学習をするのは理に適っていると言えます。
キンダーガーテン~小学1年生(5~7歳)
アメリカでは、日本の幼稚園年長さんにあたる5歳から、キンダーガーテンに通います。キンダーガーテンは、小学校入学前の子供たちが通う学校です。
英語と算数の授業は毎日あり、それ以外にアート、音楽、体育、コンピュータの授業も入ってきます。アメリカではコンピュータの授業がこのころから始まります。
フォニックスに関しては、プリスクールで学んだことを実践的に深く学習していきます。プリスクールでは、文字を書いたりはしませんでしたが、文字を書いたりして、スペルと音の関係性を学びます。
フォニックスを学ぶと、発音とスペルのルールが分かり、発音を聞いたら何でもそのスペルが分かるのかとそうではなくて、例外もあります。フォニックスのルールがあてはまる英単語は、全体の7~8割だと言われていて、残りの2~3割はそのルールがあてはまりません。
「例外2~3割は多いなぁ、そんなに例外が多いのなら、そのルールを覚えるのはしんどいな」と思われるかもしれません。でも、アメリカのような英語圏の国では、その例外の単語もこの時期から覚えていきます。発音とスペルのルールが適用されない単語は、sight wordsと呼ばれています。
まとめ
筆者が英語学習を始めた時も、もちろんフォニックスという言葉は聞いたこともなく、子どもに英語を教えだして初めて知った学習法でした。
流れるようなリズムで、♪A is for ア、ア、ア apple というのを毎日繰り返していくうちに、幼い子供も覚えていき、ある程度大きくなったら単語を推測して読めるようになっていたのは事実として見てきました。
海外の絵本やテキスト(特にイギリスの物に多かった)は韻を踏んだフォニックスを意識したものが多く、欧米の子ども達は、絵本や歌から自然に発音を習得するという話も聞いたことがあります。
日本ではまだまだとはいうものの、フォニックスが以前よりずっと身近になってきたと言えるでしょう。
アメリカやイギリスなど英語圏の国では、幼児の頃からしっかりフォニックスを学んでいきます。「アメリカにおけるフォニックス」についても紹介したので、幼児の頃の英語教育が、日本とはかなり違うことが伝わったのではないでしょうか。
フォニックスは幼児から小学校低学年に学ぶものというイメージが強いですが、英語学習の初期の頃にフォニックスを導入することで、英語の発音とスペルの関係性の理解という点において役割を果たしていることは確かです。
これを知っていればもっと自分の発音やスペルの推測力も違っていたかも、と少し悔しさを感じてしまいます!




