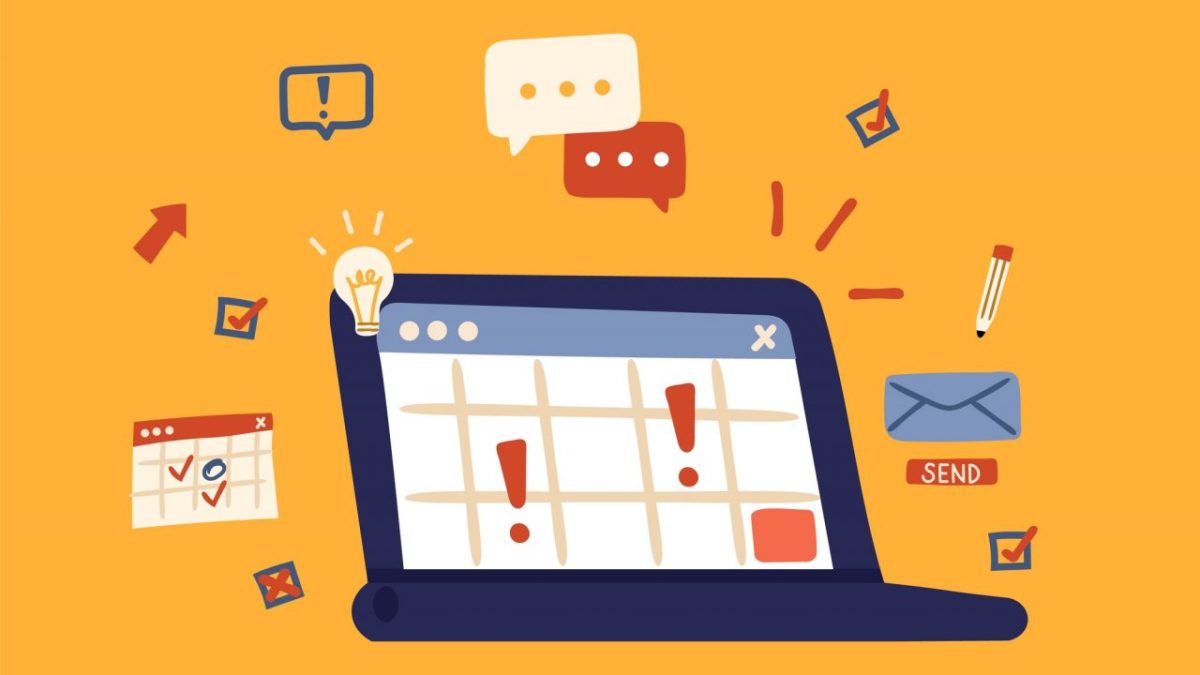昨今はオンラインで英会話のレッスンが受けられるサービスが増えており、幅広い層から注目を集めています。しかし、中にはトラブルや詐欺などが起きている危険なオンライン英会話サービスもあるので、利用するときは慎重に選ばなければなりません。
そこで、今回は危険なオンライン英会話のトラブル事例や詐欺の手口を解説します。さらに、危険なオンライン英会話を見極めるポイントや安心できるサービスも併せて紹介します。
危険なオンライン英会話もある

国内にはさまざまなオンライン英会話サービスがあり、どれを選べばいいか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。サービスによって入会金や月額料金に違いがあることに加え、レッスン時間やコースの内容が異なるので、自分に合ったサービスを見つけるのが大切です。
ただ、オンライン英会話サービスの中には、危険なサービスがあるのも事実です。そのため、危険なオンライン英会話サービスを利用しないように、しっかりと対策しておく必要があります。
そのためには、危険なオンライン英会話のトラブル事例や詐欺の手口を知っておくことのほか、見極めるポイントを理解しておくことが大切です。
危険なオンライン英会話のトラブル事例
危険なオンライン英会話といっても、具体的にどのようなトラブルが起きているかわからない方もいるでしょう。ここでは、実際に起きたトラブル事例を詳しく見ていきましょう。
運営会社が倒産
日本には大小問わず、数多くのオンライン英会話サービスがあります。大手学研グループが運営しているKiminiオンライン英会話といったサービスから、個人が運営しているようなサービスまで、幅広くあるのが特徴です。
ただ、業態の規模によっては、経営状況が安定しておらず、突然倒産してしまうケースも少なくありません。実際、ここ10年以内に倒産した企業も多くあり、中には利用者に対してレッスン料の返金をしていないところもあります。
オンライン英会話ではないですが、近年、大学受験予備校などを含む、学習塾の倒産が相次いでいます。2025年1月4日、大学受験予備校「ニチガク」を運営する日本学力振興会(東京都新宿区)が事業を停止し、負債約1億円を抱えて破産申請の準備に入ることになり、受験シーズンを前に大混乱を招きました。
2024年の学習塾は負債総額が117億4400万円で、2023年(12億6600万円)から9.2倍に増加。2000年以降で過去最多となっています。
参考:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2501/09/news035.html
しつこい勧誘
オンライン英会話サービスの中には無料体験レッスンを用意しているところがあります。実際にサービスに申し込む前に、体験できるので、オンライン英会話を検討している方は無料体験を活用することをおすすめします。
ただし、サービスによっては、無料体験後にしつこい勧誘や無理な営業をしてくるところがあります。さらに、一度断ったとしても、メールや電話などで継続して勧誘されるケースがあるので、注意が必要です。
危険なオンライン英会話の詐欺の手口
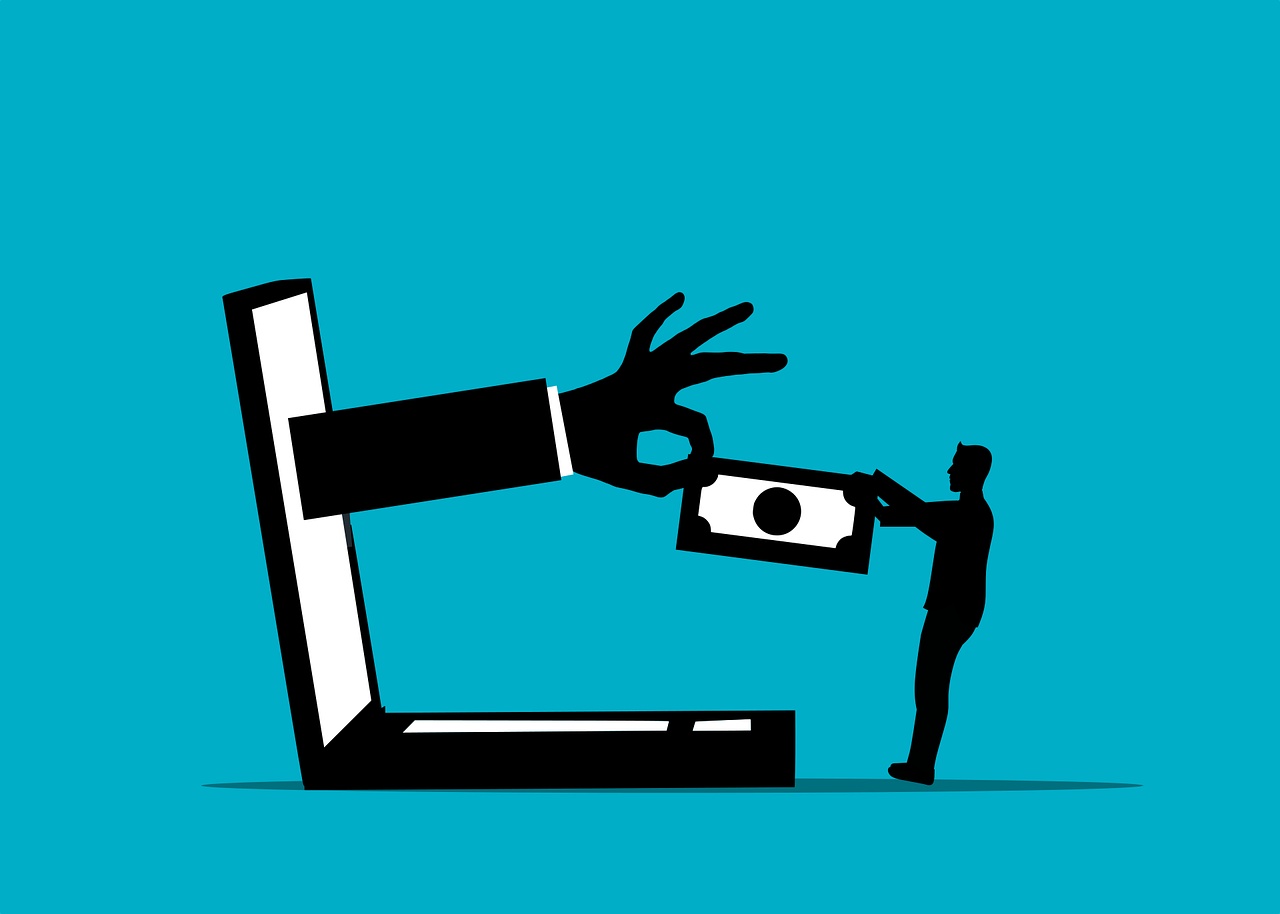
オンライン英会話を運営する会社が倒産したり、しつこい加入があったりなど、さまざまなトラブルがあります。しかし、オンライン英会話の中には、さらに悪質なサービスがあるのも事実です。
ここでは、危険なオンライン英会話の詐欺の手口を見ていきましょう。
プライベートへ誘引する
オンライン英会話のレッスンを何度か受けていると、講師と仲良くなることも少なくありません。そのため、レッスン中に日常会話やフリートークをすることもあるでしょう。ただ、その流れで、プライベートに誘われて、詐欺被害に遭うケースがあるのです。
女性講師が男性のレッスン受講生に対して連絡先を聞き、「日本に会いにいきたいけど、お金が足りない」といって、金銭を要求するといった手口があります。
怪しい投資話
レッスンを通して、講師とさまざまな話をしている中、投資話を持ちかけられ詐欺被害に遭うといったケースがあります。オンライン英会話のレッスン中にお金や投資の話題になり、受講生が興味を持ちそうな投資話を持ちかけ、出資させるといった手口です。
教材などの押し売り
オンライン英会話のレッスンを受けている方は、できるだけ早く英語を上達させたいと思っている方がほとんどでしょう。しかし、上達したいという強い気持ちにつけこんだ詐欺が発生しています。講師が「この教材を使えば、もっと英語が上達する」といい、いろんな教材を購入させるケースがあります。
レッスン受講生は、英語を上達させるために、講師の話を信じて教材を購入してしまいますが、実際は高額な教材であったり、市販品の内容とほとんど変わりがなかったりすることもあるのです。
危険なオンライン英会話を見分けるポイント

トラブルや詐欺が起きている危険なオンライン英会話もあるので、これからオンライン英会話の申込を検討している方は、しっかりとサービスを見極める必要があります。
ここでは、危険なオンライン英会話を見分けるポイントを見ていきましょう。
講師の数が少ない
危険なオンライン英会話サービスを見分けるひとつのポイントとして挙げられるのが「講師の数」です。では、なぜ講師の数が少ないところは危険な可能性が高いのでしょうか。
まず、講師の数が少ないということは、新しい講師を雇用する資金がないことを推察できます。また、実際にレッスンを受講している生徒の数が少なく、経営が安定していない可能性も考えられるでしょう。
経営が安定していないと、急に倒産してしまい、レッスン料を返金してもらえないケースもあります。さらに、講師に対しては十分な賃金を支払えておらず、質の高いレッスンを受けられないこともあるでしょう。
とはいえ、講師の数だけで判断することは難しいです。ただ、経営状況を判断するためのひとつの指標として理解しておくことが大切です。
サポート体制が整っていない
オンライン英会話を運営する会社のサポート体制が整っていないのも危険なオンライン英会話サービスかどうかを見分けるポイントのひとつです。サービスを利用するうえで、何かわからないことや、トラブルが発生しても、しっかりと対応してくれない会社には注意が必要です。
レッスンのことで何か問い合わせをしても、なかなか返信が来ないオンライン英会話サービスは、サポート体制が整っておらず、トラブルへの対応もきちんとしてくれない可能性が高いです。
レッスン料の先払いをさせる
学習塾・予備校の倒産が増えていますが、倒産に至った学習塾や予備校の多くは、破産申請をする前に学費の先払いをさせていました。2025年1月に破産申請した「ニチガク」も2024年、経営不振に陥っていたとき、学費の先払いをさせていたことが問題になっています。
オンライン英会話についても、数ヵ月先までのレッスン料の先払いを要請してきたら、怪しいと思った方がいいでしょう。
まっとうなオンライン英会話は、レッスン料は月額払いで、数カ月先まで先払いさせることはまずありません。
狭い年齢層にターゲットを絞り、内容を特化しすぎている
学習塾によく通う年齢層は6歳から18歳ですが、「学習塾指数と人口(6歳~18歳までの合計)の推移」を表す経済産業省の調査があります。
参考:https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20240321hitokoto.html
この調査を見ると、2013年には1500万人ほどいた子どもが2023年には約1350万人まで減っており、やはり少子化がかなり進んでいることが分かります。その減少に合わせて、学習塾の指数も減っており、学習塾の倒産が相次いでいるのも納得できますね。
経済産業省の調査によれば、「学習塾の売上高及び受講生一人あたりの学習塾売上高を指数化した推移を見ると、売上高指数は2020年を除き、おおむね増加傾向で推移している」とのことですが、幅広い年齢層・内容をカバーしている学習塾のみが売上を伸ばしています。つまり幅広い年齢層・内容をカバーしていない学習塾は、経営が厳しくなり倒産に追い込まれているということのようです。
学習塾に関しては、小学生のみ、中高生のみという特化型が良さそうに思えるかもしれませんが、狭い年齢層・内容に特化しすぎていると、少子化が進行して、経営を続けていくのが厳しくなることが予想できるので、幅広い年齢層、内容をカバーしている学習塾の方が安心安全だと言えます。
SNSの投稿が止まる
学習塾業界は、少子化で苦しんでいる業界なので、生徒の勧誘や定着を促すためにもSNS戦略を有効に活用するのが当然だと言えます。
最近、倒産したニチガクは、SNSへの投稿にあまり熱心でなかったようですが、公式アカウントは2022年5月3日の「毎年、多くの生徒が上智大学に合格しています」という投稿が最後だったようです。インスタグラムはニチガク予備校新宿本校という教育コンサルタントが投稿をしていて、2024年6月くらいまでは積極的に発信をしていましたが、それ以降、投稿が止まっていました。
SNSの投稿が定期的に行われているか、止まっていないかも経営がうまく続いているかを判断する基準の1つになります。
英会話塾業界の今後の展望
幼児、小学生、中高生などの一部だけをターゲットにした英会話塾は、今後ますます経営が厳しくなることが予想されます。やはり幅広い年齢層をターゲットにして、さまざまなトピックや内容を取り扱っている英会話塾が生き残っていくでしょう。
英会話塾業界も他の業界と同様に、SNSを活用して自社のビジネスを宣伝していますが、今後その広告宣伝でフェイクニュースが増えていくのかもしれません。
というのは、アメリカのMeta社の会長 兼CEOのマーク・ザッカーバーグ氏がトランプ大統領に擦り寄って、「今後アメリカのFacebookではファクトチェックを行わない」と発表したからです。ファクトチェックを行わないのは、アメリカのFacebookだけとされていますが、日本のSNSも今後その影響を受けて、フェイクニュースや偽の宣伝広告が出回るかもしれません。
安心できるオンライン英会話サービスとは
危険なオンライン英会話のレッスンを受けないためにも、安心できるサービスを選ぶ必要があります。とはいえ、どのサービスが安心できるのか、わからない方が多いのではないでしょうか。
まず、安心できるオンライン英会話サービスを選ぶときは、運営している会社の規模を確認しましょう。会社の運営規模が小さいと、倒産リスクが高い可能性があるので、できれば避けたいところです。
また、講師の数を確認することも大切です。運営期間は長いものの、講師の数が10名程度であれば、経営に何かしらの問題をかかえている可能性が高いといえるでしょう。
そのため、経営基盤がしっかりしており、講師の数が多いオンライン英会話サービスを選ぶのがポイントです。学研グループが運営しているKiminiオンライン英会話は、母体が学研であり、経営基盤がしっかりしていることから、倒産リスクが低く、安心して利用できるでしょう。
加えて、講師に質が高く、在籍人数も多いことから、自分に合った講師を探せるのも特徴です。そのほか、全163コース(2024年1月現在)から自由に選べるので、目的に合わせてコースを選択し、短期間で英語力アップを目指せるでしょう。
また、狭い年齢層にターゲットを絞り、内容を特化しすぎている学習塾も経営上のリスクに直面する可能性が高いです。今後も少子化が進むことが予想されますので、大手の予備校でさえ小学生もターゲットにしたスクールを運営し始めています。
まとめ
オンライン英会話の利用を検討しており、どのサービスに申し込もうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。ただ、オンライン英会話の中には、トラブルが多発していたり、詐欺をおこなっていたりなど、危険なサービスもあるので、慎重に選ばれることをおすすめします。
オンライン英会話を利用するときは、危険なサービスを選ばないためにも、安心できるサービスの選び方を知っておくことが大切です。
本記事で紹介した危険なオンライン英会話の見分け方と、安心できるサービスの特徴を参考に、自分に合ったオンライン英会話サービスを選びましょう。