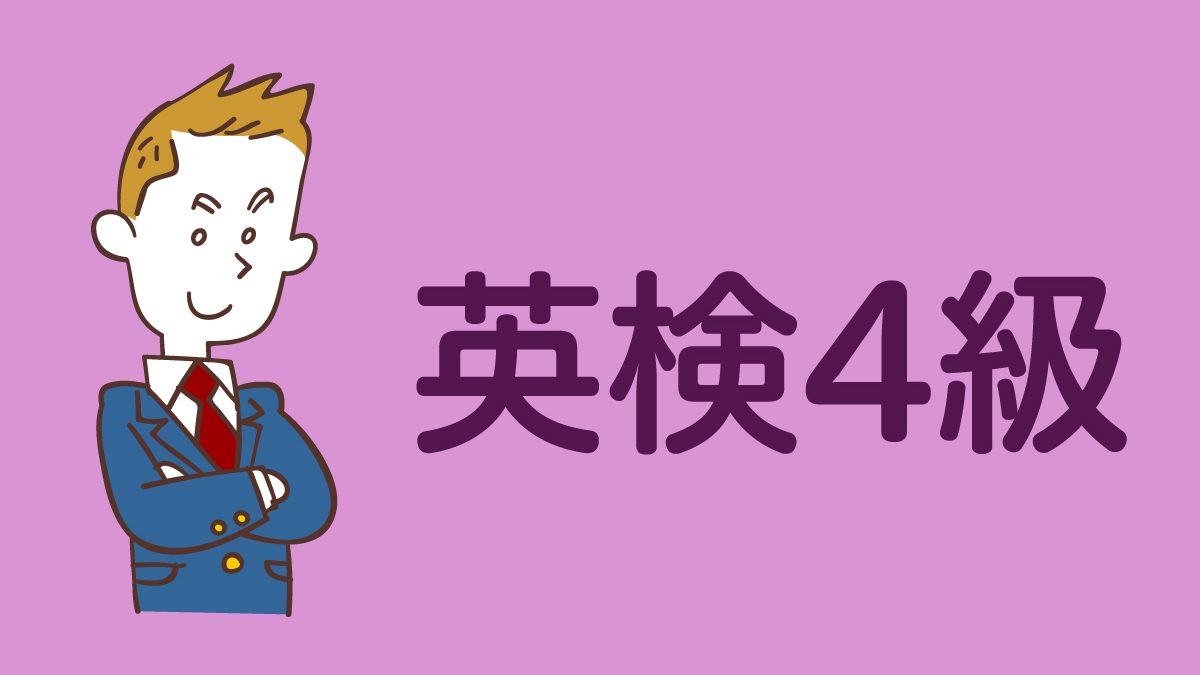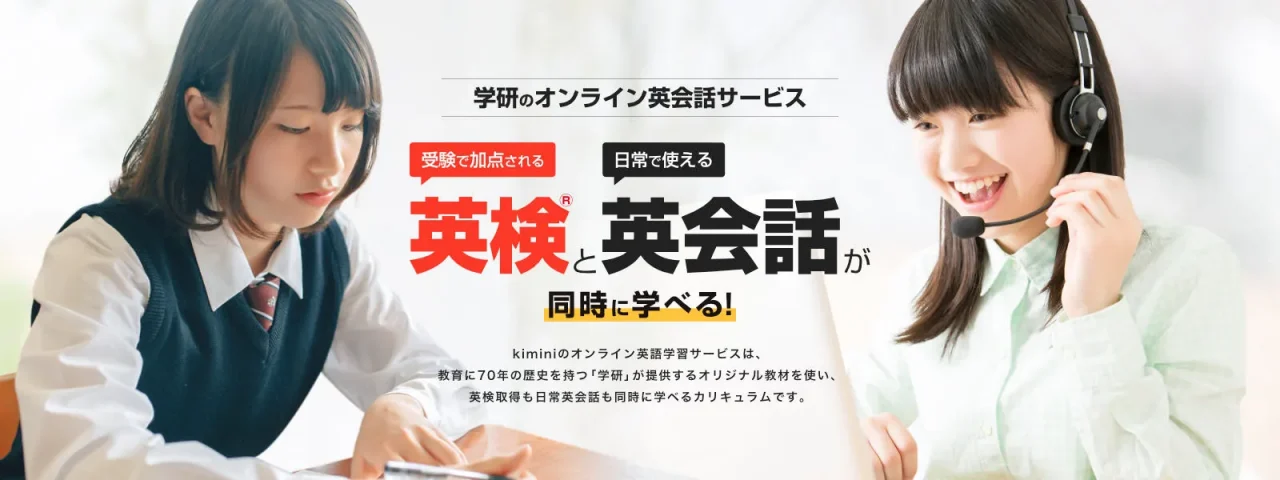英検4級は一般的には、中学2年までに学ぶ英語の内容を理解できているのかを測る試験とされていますが、実際には、小学校高学年から中学生向けの試験となっています。試験内容は、基本的な英語の会話やリスニング、そして簡単な文法を含む問題が出題されます。この試験を通じて、英語の基礎をしっかりと固めることができます。
勉強法としては、教科書に沿った基礎的な単語や文法を覚え、リスニングの練習を日常的に行うことが重要です。具体例として、英語のアニメや子供向けの英語番組を視聴することで、楽しみながらリスニング能力を高めることができます。また、単語カードを使って効率的に語彙を増やすのもおすすめです。これらの方法を活用することで、英検4級に向けた準備がより効果的になるでしょう。最終的に、英語学習を楽しむことが合格への近道です。
2020年度から英語教育が小学校5年生から教科として必修化され、英語を学び始めた生徒さんだけでなく、その親御さんからも関心が高い試験でもあります。英語は学年によって授業の内容や学習目標が異なり、3・4年生は「外国語活動」、5・6年生は「教科」となっています。
この記事では、英検4級について、最新情報とどれくらいのレベルの試験なのか、合格するにはどれくらい問題に正解すれば良いのかについてお伝えしていきます。
2026年度の試験日程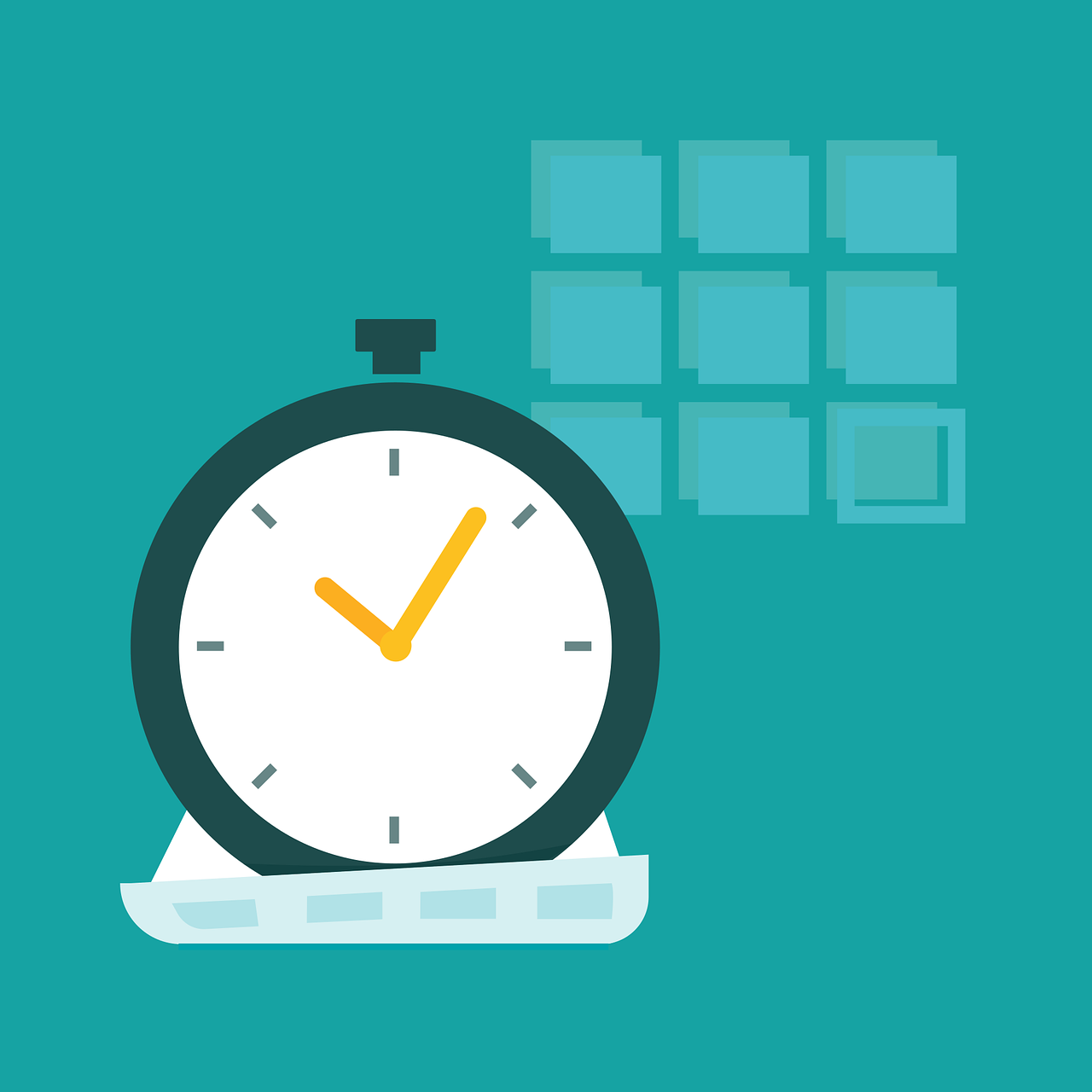
まず、2026年度の試験日程を確認しておきましょう。
個人受験と団体・学校受験で試験日程が違いますので、ご注意ください。
2026年度の個人受験の日程は、こちらのリンクで確認できます。
https://www.eiken.or.jp/eiken/schedule/2026-examinee.html
2026年度の団体・学校受験の日程は、こちらのリンクで確認できます。
https://www.eiken.or.jp/eiken/info/2025/pdf/20251112_info_eiken2026.pdf
2026年度に受験を検討されている方は、試験日程を確認し、合格に向けて準備していきましょう。
英検4級の英単語と文法のレベル
英検を主催している日本英語検定協会によると、英検4級は以下のレベルとされています。
推奨目安:中学中級程度
出題目安:出題形式や内容が、より実用的に。身近なトピックを題材とした読解問題が加わります。基礎力をぐんぐん伸ばしていきましょう。
日本英語検定協会公式ホームページより抜粋
このように、英検の最初級である英検5級に比べて「英語学習を始めてからしばらくが経ち、より実用的な英語と読解ができるようになるのが目標」になることがわかります。
ただし「中学中級程度」と言われると少し抽象的で、以下のように思う方もいらっしゃるかと思います。
もう少し具体的に、英検4級のレベルについて深掘りしましょう。
英検4級を目指すにあたり、日常的に英語に触れる機会を増やすことが重要です。例えば、英語のアニメや音楽を楽しんだり、オンラインで英語を使ったゲームをプレイすることが、自然な形での学習につながります。これらの方法を通じて、楽しみながら英語力を高めていきましょう。
英検4級の単語レベル
英検4級では、中学校1年生から2年生程度の英語の知識が求められます。具体的には、英単語では日常生活でよく使われる基本的な語彙が中心で、動詞や名詞、形容詞といった品詞の理解が重要です。
英検4級の英単語レベルはおおよそ1300語〜1400語レベルだといえます。
これは小学校で習う英単語数に加えて、英検4級合格を目指す英単語帳が約700語の英単語を収録していることから算出できます。
なお小学校で習う英単語数は、文部科学省の中学校学習指導要領解説から「600語〜700語」だとわかります。(参照↓)
実際のコミュニケーションにおいて必要な語彙を中心に、小学校で600〜700語程度(中略)を指導することとして整理している。
小学校で習う英単語が600語〜700語、英検4級合格の英単語帳で新しく700語が加わることで、「英検4級の単語レベルは約1300語〜1400語程度」だといえるわけですね。
それでは、もっと具体的に「1300語〜1400語レベル」がどんな英単語かを見てみましょう。
日本英語検定協会は、実際に出題された英検各級の過去問を公式ホームページで見ることができます。
その中から、英検4級で実際に出題された過去問をいくつか見てみましょう。
A : How much time do we have before the ( ) train?
B : About five minutes.1, lost 2, clear 3, next 4, heavy
A : Oh no! I wrote the wrong date. Can I use your ( )?
B : Sure. Here you go.1, belt 2, eraser 3, coat 4, map
2022年度 4級第一回実用英語技能検定より抜粋
これは主に英単語力を図る大問1の抜粋です。シンプルに単語の意味を知ってるかどうかを問われる問題がほとんどですね。
英単語力がどのように出題されるかを見たところで、他にも英検4級で出題されている英単語をリスト化するので、「英検4級で出題される英単語はこういうレベルだ!」という感覚を得るのに役立ててください。
- since
- through
- address
- temperature
- send
- bore
- weak
- careful
- trouble
- moment
2022年度 4級 第一回実用英語技能検定より抜粋
英検4級の文法レベル
英検4級で問われる英文法レベルは、中学1年生〜2年生程度のレベルです。文法に関しては、現在形や過去形、進行形といった基本的な時制の使い方、疑問文や否定文の作り方が問われます。
中学校で学ぶ英文法項目の詳細は文部科学省 中学校学習指導要領解説 外国語編(平成29年 7月)の付録7にて確認できます。(137ページ)
実際に英検4級の過去問を3回分確認してみると、以下の文法問題を確認できました。
- 助動詞Shallの用法
- 過去形(特に不規則動詞)
- 動名詞
- 不定詞
- be going toの用法
- 許可を求めるCan I ~?を丁寧にするCould I〜?の表現
- 時制の一致問題(過去形)
- There is/are の構文
- 比較級 や more and moreの表現
- 人称代名詞目的格
さらに、英検4級では大問3で語句整序問題(単語やフレーズを並び替えて正しい英文にする問題)が出題されるので「英語の語順」という側面でも英文法知識が必要です。
ただし、試験全体の出題数で言えば、純粋な英文法力を問われる問題は英検の性質上少ないといえます。(具体的には大問1の15問のうち4問程度が文法問題)
大問1の文法問題を過去問から抜粋して紹介します。
A : There ( ) many interesting animals at this zoo.
B : Yes. I want to come here again.1. is 2. are 3. am 4. be
A : Is skiing ( ) than snowboarding, Tom?
B : Sure. Here you go.1. harder 2. hard 3. hardest 4. too hard
A : Did you get any food at the baseball stadium yesterday, Linda?
B : Yes. I ( ) two hot dogs. They were delicious.1. eat 2. eating 3. eats 4. ate
2024年度 4級第三回実用英語技能検定より抜粋
There is ~か There are ~を問う問題は、英検4級ではよく出題されます。be動詞の後が単数や物質名詞なら is で、複数形ならare になります。上の文では、animals と複数形が来ているので、答えは 2. are となりますね。
4級では比較級の問題もよく出題されます。後ろに”than”があれば、比較級なので、短い単語であれば -erの形、3音節以上の長い単語の場合は、”more ~”で比較級を作ります。上記の問題では、答えは1. harderとなります。
また、不規則動詞の過去形を問う問題もよく出題されます。上記の最後の問題では、eat の過去形の 4. ateが正解ですが、不規則動詞の過去形がすっと出てこない生徒さんもいます。
大問1の文法問題はあまり難しくないので、英検4級の文法対策は、文法の知識を必要とする語句整序問題の対策がメインになるでしょう。
英検4級の読解問題対策
英検5級にはなかった読解問題が、英検4級から追加されます。大問4はA. 掲示板の広告、B. Eメール問題、C. 長文 の3題から構成されます。
5級はすんなり合格できたのに、4級になって難しくなったと感じる小中学生が意外と多いのは、読解問題のせいもあるでしょう。小学生で4級を受ける場合、なおさらそう感じるでしょう。
4級の3題の読解問題は、3級以上と比べるとそんなに長くないのですが、小中学生にとっては長く感じる人がおられるでしょう。
大問1~3までがほぼ完璧にできたら、大問4はあまりできなくても合格できるという意見もありますが、読解問題を完全にあきらめてしまうのは、もったいないです。
大問4の読解問題は、解き方にコツがあります。まず、必ず質問に目を通してから、読解文を読むようにしましょう。質問で何を聞いているのか疑問詞に注意して読むことが重要です。
質問に関連する部分だけを読むだけで、答えられる問題もありますが、選択肢では、読解文の該当箇所を少し違う表現に言い換えているものが多くなってきています。
英検4級のライティング対策
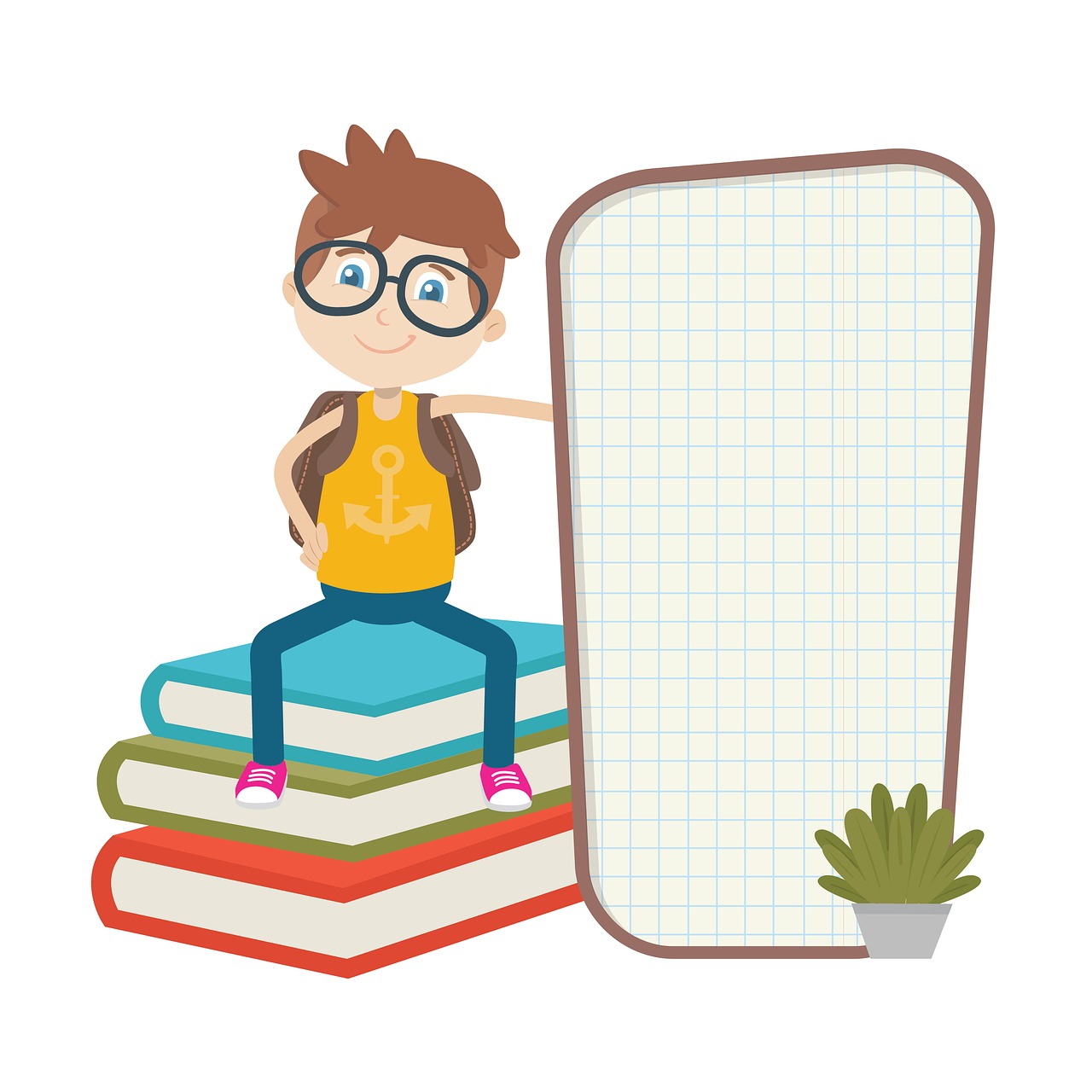
英検4級のライティング対策は、英検5級と同じく大問3の語句整序問題がメインになるでしょう。
理由については英検5級と共通なので、以下を参考にしてみてください。
英検 4級のライティング対策は、大問3の語句整序問題の対策がメインになります。
なぜなら、英検中上位級(3級〜1級)までは筆記での英作文問題が出題されないからです。
なので、英作文の要素を含んだ語句整序問題が実質のライティング科目だといえます。
語句整序問題では、英語の語順やかんたんな構文を理解しているかを問われます。
ここにリンク→英検5級のレベルは?どんな問題が出る?わかりやすく解説します
要約すると、「筆記の作文問題は5級と4級では出題されないので、英作文に似た語句整序問題(英単語を並び替えて正しい英文にする問題)の対策が実質上、英検4級のライティング対策になる」ということです。
語句整序問題の対策は、ドリル形式の参考書や解説付きの過去問で対策するのがおすすめです。
英検4級のリスニングテスト対策
英検4級のリスニングテストは、第1部から第3部まで、それぞれ10問ずつで30問が出題されます。
第1部は、イラストを参考にしながら、男女の対話文を聞き、その後に続く表現を1~3の選択肢の中から1つ選びます。
第2部は、男女の対話を聞き、その質問に対して適切なものを1~4の選択肢から選びます。
第3部は、2、3文から成る英文を聞き、その質問に対して適切なものを1~4の選択肢から選びます。
すべての問題が2回ずつ繰り返して読まれます。英語のリスニングに慣れている人や海外在住のお子さんにとっては、あまり難しくないでしょうが、リスニングに慣れていないお子さんにとっては、2回繰り返して読んでいても、難しく感じるでしょう。
リスニングテストの過去問を通して解いてもらい、答え合わせをして、どこができなかったのかを確認し、間違えた問題を中心に英文スクリプトをチェックしましょう。過去問を解いて、どこを間違えたのか、どういう問題が苦手なのかを把握し、対策を講じることが重要です。
英検4級の合格点

英検4級の合格点は毎回の試験ごとに異なります。なので「何点取れば合格!」とは断言できません。
ただし、「各技能(リーディングやリスニングなどのこと)で、6割~7割程度以上の正解率で合格できる可能性が高い」といえます。
なぜなら「英検CSEスコア」と「英検協会ホームページの言葉」から読み取れるからです。
「英検CSEスコア」とは以下の特徴を持つ採点方式を指します。
2016年度の試験から、英検は採点方式を「英検CSEスコア」という独自の方式に移行しました。
英検が英検CSEスコアを採用した背景として、「各技能(リーディングやライティングなどのこと)で点数に偏りがある受験者よりも、各技能でまんべんなく点数を取れる受験者が合格しやすい仕組み」を取ったことが挙げられます。
また、英検を主催している日本英語検定協会の公式ホームページからは以下の言葉が記載されています。↓
正答数の目安を提示することはできませんが、2016年度第1回一次試験では、1級、準1級は各技能での正答率が7割程度、2級以下は各技能6割程度の正答率の受験者の多くが合格されています。
以上の「英検CSEスコアの性質」と「英検協会からの言葉」から、「各技能(リーディングやリスニングなどのこと)で、6割から7割以上の正解率で合格できる確率が高い」と言えるわけです。
英検4級合格に向けた勉強法
英検4級に合格するためには、基本的な英語能力をしっかり身につけることが重要です。特に、中学校で習う基礎的な文法や単語の理解が求められます。まずは、教科書や参考書を使って、英語の基礎を固めることから始めましょう。次に、リスニングの練習を強化するために、音声教材を活用すると良いです。例えば、英語のポッドキャストやオンラインのリスニング教材を日常的に耳にすることで、耳を英語に慣れさせることができます。また、過去問を繰り返し解くことで、試験の形式に慣れ、時間配分の感覚を掴むことができます。さらに、英単語を効率的に覚えるために、フラッシュカードアプリなどを利用するのも効果的です。これらの方法を組み合わせて、全体的にバランスよく学習を進めることで、英検4級の合格に近づくことができるでしょう。
効率的な単語と文法の学習法
英検4級を目指すにあたり、効率的な単語と文法の学習法を知ることは重要です。まず基本的な説明として、単語に関しては日常生活でよく使われるものを中心に覚えることが効果的です。具体的なアドバイスとして、テーマ別に単語をまとめることで、関連づけて覚えやすくなります。例えば、学校や家庭で使う単語をリスト化し、毎日少しずつ覚えていく方法があります。
また、文法に関しては、中学1・2年生レベルの基本的な文法事項をしっかりと理解することが重要です。実践的なポイントとして、文法書を使いながら例文を作成し、実際に声に出して読むことで、文法の使い方を体感的に学ぶことができます。このような方法を活用することで、単語と文法の両方をバランスよく学習し、英検4級の合格を目指しましょう。
読解問題の解き方とコツ
英検4級の読解問題は、短い文章を読み、その内容を理解する力を試すものです。まず、問題に取り組む前に、設問をしっかりと読み込むことが重要です。これにより、何を探すべきかが明確になります。続いて、本文を読む際は、主語や動詞に注意を払いながら、段落ごとの要点をつかむよう心がけましょう。具体的なコツとしては、知らない単語があっても前後の文脈から意味を推測する技術を磨くことが挙げられます。また、本文を読み終えたら要点をまとめることで、設問に対する答えを見つけやすくなります。注意点として、焦らずに時間をかけて内容を理解することが大切です。練習を重ねることで、読解力は徐々に向上しますので、日常的に英語の文章に触れる機会を増やしていきましょう。
リスニング対策のポイント
英検4級のリスニング対策には、日常的な英語の音に慣れることが重要です。まず、基本的な英語の音声を聞く習慣をつけましょう。例えば、英語のアニメや子供向けの番組を活用することで、楽しくリスニング力を鍛えることができます。また、公式問題集のリスニング問題を繰り返し練習することで、出題傾向や問題形式に慣れることも大切です。具体的には、聞き取った内容をメモする練習をすると、細かい情報を逃さず理解する力がつきます。さらに、リスニング後に内容を声に出して復唱するシャドーイングも効果的です。これにより、リスニング能力を高めるだけでなく、発音やイントネーションの改善にもつながります。
小学生向けの勉強時間と学習計画
小学生が英検4級に挑戦する際の勉強時間と学習計画を立てることは非常に重要です。まず、基本的な説明として、英検4級は中学初級レベルの英語力を問う試験で、小学生の場合、少しハードルが高いかもしれません。
しかし、きちんとした計画を立てることで目標達成は可能です。例えば、毎日30分から1時間程度の勉強時間を確保するのが理想的です。具体的には、平日は学校の宿題が終わった後に、週末は少し長めに時間を取ると良いでしょう。実践的なポイントとしては、単語帳を使った語彙の強化や、リスニングの練習を欠かさないことが重要です。また、英語の絵本やアニメを利用して、楽しみながら学ぶ方法も効果的です。注意点として、無理のない範囲で継続することが大切です。楽しみながら学ぶことで、英語への興味を持ち続けることができます。
塾やオンライン英会話の活用方法
英検4級を目指す小学生には、塾やオンライン英会話の活用が非常に効果的です。まず、塾に通うことで、英語の基礎をしっかりと学ぶことができ、特にリスニングや文法の理解が深まります。経験豊富な講師が、個々の生徒のペースに合わせて授業を進めてくれるため、効果的な学習が期待できます。
オンライン英会話は、場所や時間に縛られずに学べる点が魅力です。ネイティブスピーカーとの会話を通じて、実践的な英語力を身につけることができます。また、オンラインのプラットフォームでは、ゲーム感覚で英語を学べる教材も多く、子供の興味を引きやすいです。これらの方法を併用することで、英検4級合格に向けた総合的な英語力の向上が図れるでしょう。ただし、子供の負担にならないよう、楽しく学べる環境を整えることが重要です。
オンライン英会話を利用する利点には、リスニング力、スピーキング力が鍛えられるということも挙げられます。4級では二次試験のスピーキング力は求められませんが、3級以上になると、リスニングも難しくなり、二次試験でスピーキング力も求められます。3級以上へのレベルアップも見据えて、4級からオンライン英会話を導入しておくこともおすすめです。
学研のKimini英会話主催 英検合格コース
英検を運営している日本英語検定協会は、日本の教育を司る国の機関である文部科学省が後援しています。
なので、英検は学校の科目としての英語教育との相性がとても良いです。
学研は学習塾や教育サービスを古くから手掛けてきた老舗の会社です。
そんな学研の主催する英検合格コースは、学校の英語教育と相性が良い英検に非常に高い効果を期待できます。
英検4級のコースでは、どうしても筆記とリスニングに偏りがちな学校英語に比べて、しっかり「話せる英語」にも焦点があたった勉強が期待できるコースなのでぜひ参考にしてみてください。↓
まとめ
この記事では、中学で学ぶ英語の内容が理解できているかを測る英検4級についてお伝えしました。
昨今では、英検4級合格を目指して勉強している小中学生が増えています。英検4級はあまり難しくないという声もありますが、大問4で読解問題が3題出題されます。問題の数も英検5級より格段に増えますので、しっかり対策していきたいですね。問題数が増えるので、問題を解くスピードも重要になってきます。大問1や大問2を解くのに時間がかかりすぎていたら、大問4の最後まで時間内に解き切れないでしょう。
英検4級は小学生にとって、英語学習の初期段階での大きな目標となります。合格を目指すことで、英語力の基礎を固めるとともに、自信を持つことができるのです。特に小学5年生や6年生での受験が一般的で、学校の授業内容ともリンクしやすいことがメリットです。具体的には、日常的な英単語の習得や基本的な文法の理解が求められます。家庭学習では、英検の過去問を活用し、リスニングやスピーキングの練習も並行して行うことが効果的です。英語に親しむことで、将来の学習意欲を高め、他の言語や文化への興味も育まれるでしょう。これらの経験は、子どもたちの成長に大きく寄与します。
「英検4級に本気で合格したい(合格させたい)」と思ったら、過去問や練習問題を解くときに、時間を計って解く練習をするといいです。時間内に大問4の最後まで解き切れなかったら、問題を解くスピードや時間配分にも気を配りましょう。
英検4級は過去問や練習問題をたくさん解いて、しっかり準備をすれば合格できる試験ですが、問題数が増えているので、時間を計らずにマイペースで解いて準備していたら、予想外の結果に陥るかもしれません。
英検4級は、読解問題が3題出題されて全体の問題数が増えるため、時間配分を意識しながら、問題を解く練習をする必要があります。読書する習慣がない子どもが増えている中、英検4級でつまづくお子さんも一定数おられます。
「読解問題が苦手」、「リスニング問題が苦手」など苦手パートの対策には、個別レッスンが効果的です。Kiminiオンライン英会話の英検4級®合格コースは、リーズナブルな料金で気軽に始められて、英検4級合格のための対策がしっかりできるので、試してみられてはいかがでしょうか。自宅でレッスンが受けられるので、送り迎えが要らないという利点もあります。
ここまでお読みのあなたは、英検4級に向けてまず何に取り組めば良いか、どんなレベルの問題が出るのか、どれくらい問題に正解すれば良いかについての知識を十分に持っているでしょう。
この記事でお伝えしたことが、英語学習をより豊かにできれば幸いです。