英検1級は、日本で最も難しい英語試験のひとつです。英検1級の一次試験に合格したら、二次試験にも合格して、英検1級合格証書が欲しいところですが、英検1級一次試験の合格通知を受け取ってから、二次試験の本番までには2週間ぐらいしかありません。2週間ぐらいで二次試験対策を完ぺきに仕上げるのは厳しいですね。
この記事では、英検1級の二次試験に合格するためのコツについて解説します。準備方法や評価点についても触れていますので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
英検1級の二次試験とは?

そもそも、英検1級の二次試験はどんな試験なのでしょうか。
英検1級の二次試験は、出題されるトピックの傾向に変化はあったでしょうが、問題形式は長年変わっていません。
5つのトピックから1分間で1つのトピックを選んで準備し、選んだトピックについて2分間のスピーチをします。スピーチの後、面接官2人からスピーチの内容についていくつか質問されるので、それに対して質疑応答をします。
二次試験のバーチャル二次試験とサンプル問題が英検の公式サイトに提示されているので、下記のURLからご確認ください。
1級の面接試験では、2分間スピーチの前に、面接官から2問ぐらい質問されます。その質問はバーチャル二次試験でも確認できますが、だいたいお決まりの質問です。
-
How long did it take you to get here this morning?
(今朝ここに到着するのにどれぐらいかかりましたか?) -
Could you tell us a little bit about yourself, please?
(少し自己紹介してください。)
筆者は二次試験に2回目で合格しましたが、2回とも英語で自己紹介するように言われました。面接会場に到着するのにどれぐらいかかったかについては、2回とも聞かれませんでした。
自己紹介では、学生なのか社会人なのか、何に注力して生活しているかなどを述べ、面接官から少し質問されてそれに答えます。
面接試験の冒頭の自己紹介は、評価の対象にならないとされていますが、自己紹介で流暢に話せることは、その後自信を持ってスピーチすることに繋がります。英語で自己紹介できるようにしっかり準備しましょう。
二次試験の評価点
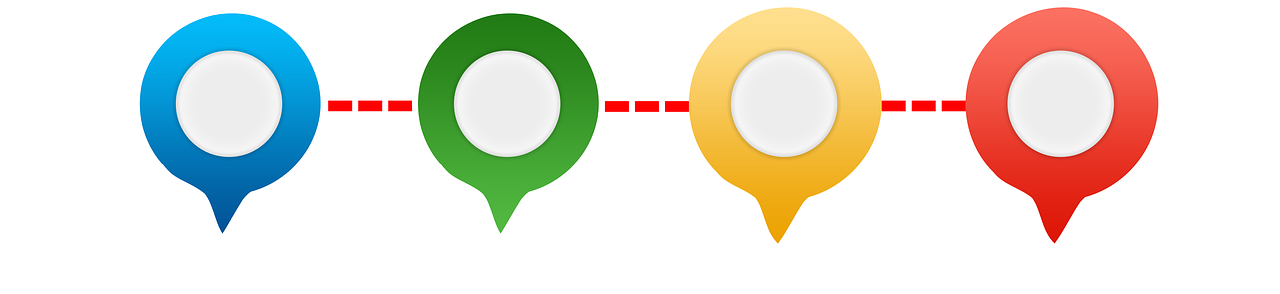
1. スピーチ、2. インタラクション(質疑応答)、3. 文法・語彙、4. 発音(流暢さ)の4つの要素で評価され、それぞれ10点ずつ配分されます。合計40点満点で、各要素で平均7点以上取る必要があります。一次試験合格者で、スピーキングもある程度できる方なら、二次試験対策をやれば、各要素で6、7点ぐらいは取れるでしょう。しかし、どれかの要素で6点があり、他の要素が7点の場合、合格は厳しくなります。
多くの二次試験受験者の評価は、6、7点が多いと考えられますが、要素ごとにどうやって点数を伸ばして合格に到達するかについて解説します。
1. スピーチ
問題カードを渡されて、1分間で5つのトピックからどれを選ぶかを決め、2分間スピーチの準備をしますが、どのトピックを選ぶかがとても重要です。5つのトピックの中には、A. 専門知識がないと説明できないものと、B. 一般的な内容のものが含まれています。サンプル問題を使って確認してみましょう。
- What role should the United Nations play in international politics?(国際政治において国連はどんな役割と果たすべきか)
- Do the rich have a responsibility to help the poor in society?(社会の中で、金持ちは貧しい人を助けるために責任を持つべきか)
- Is tradition always worth preserving?(伝統はつねに保護するに値するか)
- Should students be asked to evaluate their teachers?(学生たちは先生を評価することを要請されるべきか)
- Agree or disagree: The Olympics have become too commercialized. (賛成または反対:オリンピックは商業的になりすぎている)
日本英語検定協会 1級サンプル問題より引用
上記のサンプル問題をAとBに分類してみると、1、2、5はAに分類されます。3と4はBに分類されるでしょう。2は、経済に詳しく触れずに展開するなら、一般的な問題とも解釈できます。
バーチャル二次試験では、3が選ばれています。4は学生にとっても大人にとっても答えやすいトピックだと言えます。小中学生で英検1級に合格している人の多くは、Bのトピックを選んでいるだろうと考えられます。
5つのトピックすべてが専門知識がないと回答が厳しいものばかりなら、おそらく小中学生で1級に合格する人はもっと減るでしょう。
スピーチの後、面接官2人からそのスピーチに対する反論めいた質問をされるので、自分が専門知識を持っているトピックが見当たらないなら、一般的な内容のトピックを選ぶのが無難です。トピックの選択で失敗すると、スピーチ自体も質疑応答も厳しくなります。
2分間スピーチは、さまざまな練習問題を使って、流ちょうにスピーチできるようになるまで練習しましょう。最初に少し前置きをして、質問への答えを述べ、その理由を2つぐらい述べ、最後に結論を述べます。理由は2つにして、各理由につき2、3文で説明するのがおすすめです。バーチャル二次試験のスピーチも参考にしてください。
スピーチを2分ぴったりで終えるのは至難の業です。何度もスピーチの練習をして、2分スピーチの長さを感覚で覚えるといいですが、余裕があれば、腕時計でスピーチの長さをチェックするのもありです。
短めでスピーチを終えた場合は、面接官から“Is that all?”と聞かれます。10秒ぐらい残してスピーチを終える分には、長さについてはあまり減点されないでしょう。スピーチを30秒以上早めに終えたら短すぎるので、減点される可能性が高いです。スピーチが長くなりすぎると、面接官から”Time is up”と言われます。”Time is up”と言われても、あと数秒で結論を言い終えられるなら、最後まで言い切りましょう。タイムに関しては、プラスマイナス10秒は誤差としてみなされます。
実際、2分間スピーチで7点以上をとるのはかなり難しいです。サンプル問題はほんの一例で、本番のスピーチのトピックはさまざまなものがあります。二次試験会場でも、いくつかの部屋に分かれて面接試験を受けるので、数種類のトピックカードが準備されています。
なので、1級に合格するためには、さまざまなトピックで2分間スピーチの練習をする必要があります。
Kiminiオンライン英会話のニューストークでは、さまざまなトピックに関する語彙が学べて、講師とディカッションもできるので、ニューストークを1級の二次試験対策に活用することもできます。
2. インタラクション(質疑応答)
インタラクション(質疑応答)では、自分のスピーチに対して面接官が反論の質問をしていきます。この部分はいわゆるディベートです。その反論について、少し譲歩をするコメントを入れつつも、スピーチで述べた自分の立場を崩さないようにして、応答するようにしましょう。面接官から反論の質問をされて、簡単にそれに同意して流されてしまうようでは、スピーチで述べたことの信用が失われてしまいます。
質疑応答では、面接官の反論にも触れた方がいいので、少し譲歩するコメントを入れますが、譲歩の仕方については、バーチャル二次試験でも確認できます。
3. 文法・語彙
文法については、正しい文法を使ってスピーチをすることを意識しましょう。文法面で明らかにおかしいミスをした場合は減点されます。主節と従属節の時制がうまく合っていなかったり、物を主語にしていて受動態を使うべきなのに、受動態が使われていなかったりすると減点対象になります。
語彙については、どのトピックを選ぶかによって使える語彙が変わってきます。サンプル問題では、1は国際政治、2は社会問題、3は伝統、4は生徒と先生の関係、5はオリンピックに関する問題ですが、政治、経済、日本文化、学校関連のトピックはよく出題されるので、自分の得意な分野を選んで、その分野の語彙をたくさん覚えて、英語でニュースもチェックしておくと役に立ちます。
経済をテーマにするなら、相互関税 reciprocal tariffs、自由貿易 free trade、保護貿易 protective trade、貿易赤字 trade deficitなどの語彙を覚えて、英語でニュースもチェックしておきましょう。英検1級レベルともなると、経済関連の英語表現も知っておくべきですが、二次試験で経済のテーマを選ぶと、質疑応答で経済関連の表現を使って質問されるので、経済用語や概念に自信がない場合は、避けた方がいいです。国際政治や国連関連のトピックも、その分野にあまり詳しくない場合は、避けたいところです。
一般的なトピックを選ぶ場合、日本文化は頻出テーマの一つで、「政府は日本のボップカルチャーを保護していくべきか」などが問われます。日本のポップカルチャーとは、どんなものを含むかを確認しておく必要があります。ポップカルチャーとは、一般大衆に広く受け入れられ、楽しませる現代的な文化全般を指し、アニメ、漫画、J-POP、映画、ゲーム、SNS、ファッションなどが代表的な例です。
4. 発音(流暢さ)
スピーチで7点以上を取るのは難しく、6点になってしまう可能性がありますが、それをカバーできるのは発音(流暢さ)だったりするので、スピーチと質疑応答を通して、発音を意識ながら、できるだけ流ちょうに話すことをおすすめします。
小中学生で英検1級に合格している人は、帰国子女などが多いと考えられ、発音でバッチリ得点しているでしょう。スピーチで8点を取るよりも、発音で8点を取ることの方が容易なように感じます。
英検1級の二次試験で使える表現

1級の二次試験で使える表現は、どのトピックを選ぶかによっても違ってきますが、ほとんどのトピックで使える表現を紹介します。
1. In my opinion, …「私の意見では、…」
スピーチをI think … で始める人が多いですが、一般的な考え方と違う意見を述べる場合などに、In my opinion, I don’t think you can say …で始めることもできます。
2. It depends on …「それは…次第である」
この表現はほとんどの人が知っていますが、使いこなせている人はあまり多くないです。スピーチでも有効に使うことが可能です。
3. Some people may say that …, but I would ask … 「…と言う人もいるかもしれませんが、私は…と問いたい」
スピーチの2分は想像以上に長いので、スピーチの内容をふくらませるために、この表現は使えます。
4. In conclusion [To sum up], …「結論として(まとめると)、…」
In conclusionもTo sum upも結論を述べるときによく使われる表現ですが、その後に第一文で述べたことを少し表現を変えて述べることが重要です。
バーチャル二次試験では、To sum up, it is not possible to say … という表現を使っています。
上記以外にも、話を展開する上で、流れが変わるときにHowever,を使ったり、例を挙げるときに For example,などを使うことができます。冒頭の意見陳述、2つの理由、結論だけでは、スピーチが2分近くまでいかないので、どうやってスピーチを上手くふくらませるかを考えて、練習をしていくことをおすすめします。
二次試験で落ちる原因
英検1級の二次試験で落ちる原因としては、端的に言えば、先ほど紹介した各要素で平均7点以上取れない場合です。1. スピーチ、2. インタラクション(質疑応答)、3. 文法・語彙、4. 発音(流暢さ)の4要素ですが、すべての要素で7点以上取れないと合格できないということではなく、スピーチで6点でも、発音(流暢さ)で8点を取って、それ以外で7点を取れたら、何とか合格できます。どの要素でも、だいたい6点、7点がつくことが多いので、そこから脱却できるように努力していくことが課題になります。
まとめ
一次試験の合格は1年間有効なので、二次試験に3回まで不合格でも、4回目に合格できれば、1級の合格証書は手に入ります。5つのトピックのうち、どれを選んで2分間スピーチするかが重要です。
二次試験突破が大変でも、決してあきらめずに、1級合格を目指してがんばっていただきたいです。





