英語の勉強をしていると「原形不定詞」に出会うことはよくありますね。
「不定詞」と言えば”to”を伴(ともな)った「to不定詞」が一般的ですが、文章中の動詞に伴(ともな)って例外的に「動詞の原形」を使って不定詞を表すことがあります。それが「原形不定詞」です。
「原形不定詞」は今では中学英語で習う範囲で、特に英語の検定試験TOEICでもよく出題される英文法要素です。
この記事では、「原形不定詞」についてわかりやすく解説します。
原形不定詞とは
原形不定詞とは、文字通り「動詞の原形のまま不定詞として使われる文法要素」を指します。
ほとんどの場合、不定詞は”to 〜”の形で使われますから、「不定詞=”to ~”の形」と覚えている方がほとんどでしょう。(筆者の僕も同じです。)
ただし例外的に不定詞がto無しの「原型」で使われることがあり、それこそが「原形不定詞」と呼ばれているわけですね。
それでは、どんな時に不定詞が「原形不定詞」の形で使われるのでしょうか?
次の項から見ていきましょう。
「原形不定詞」 を使う用法
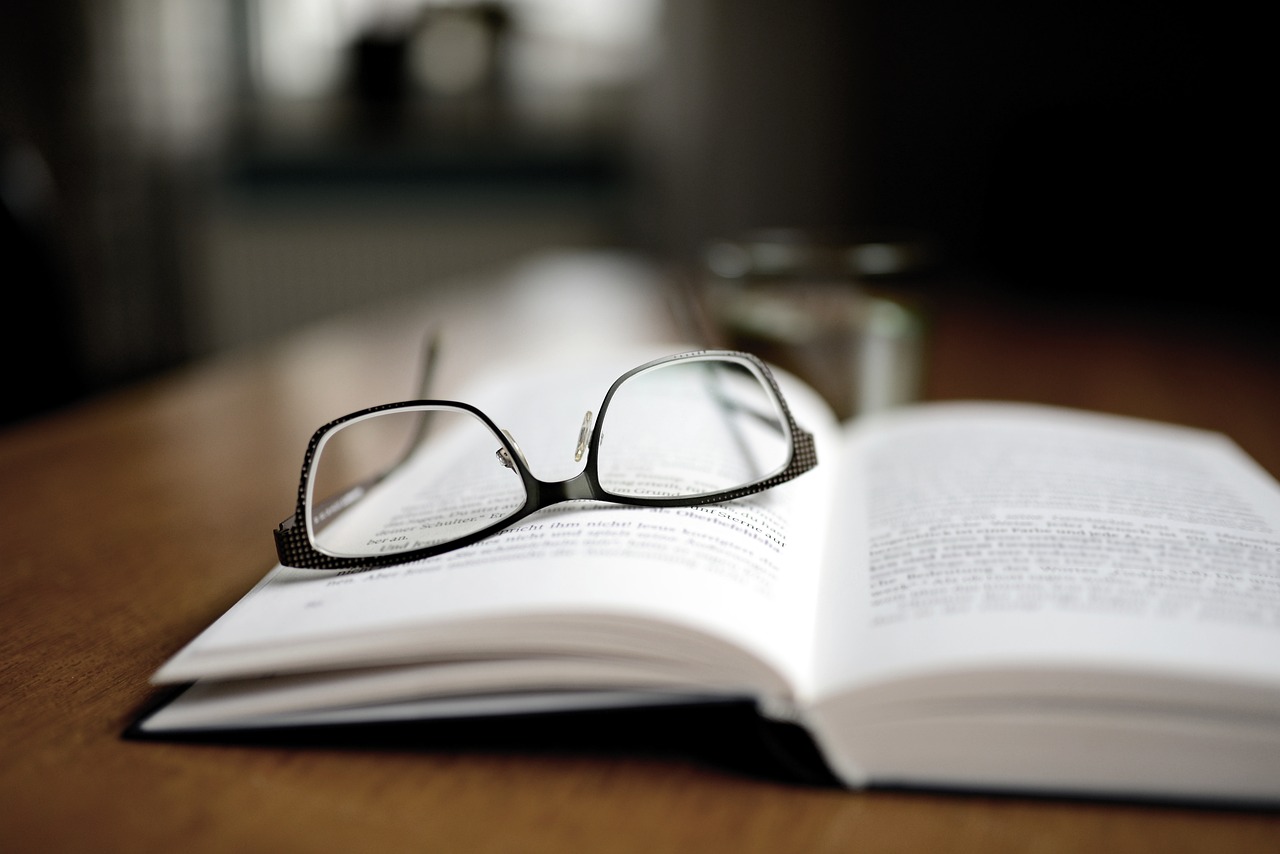
不定詞でtoがつかない「原形不定詞」を使う場面は、大まかに以下のように分けられます。
使役動詞
不定詞でtoがつかない「原形不定詞」を使う場面として、「使役動詞」が挙げられます。
「使役動詞」は、「O(目的語)をC(補語)にする」という形で使われる動詞を指します。
例えば、The cat makes me happy.(その猫は私を幸せな気分にしてくれます。)のように、動詞の”make”が起点となって、「me(目的語)をhappy(補語)にする」という形を作るのが「使役動詞」です。
「使役動詞」の「使役」は、「(誰かに)〜させる(やらせる)」という意味ですから、使役動詞の「使役」という言葉から意味を連想して覚えられると効果的です。
原形不定詞を使う使役動詞として、大きく分けて以下の3つが挙げられます。
- make
- let
- have
これら3つは、日本語に訳してしまえば「〜させる」という意味になりますが、微妙に意味や使い方が変わってきます。
順番に見ていきましょう。
make
使役動詞の”make”は「〜させる」の意味で使われます。
使役動詞は基本的に「〜させる」の意味で使われますが、使役動詞の”make”は「強制力が高い」のが特徴です。
例文を見ながら、細かい意味に注目してみましょう。
【例文】
- The teacher made us stay after class to finish our homework.
先生は私たちに宿題を終わらせるために授業後も残らせた。 - The coach made the players run five extra laps after practice.
コーチは練習後に選手たちに追加で5周走らせた。 - The CEO made all department heads submit their reports by noon.
CEO(最高経営責任者)は全ての部門長に正午までに報告書を提出させた。
例文を見ると、下線を引いた部分が使役動詞の”make”と、それに伴(ともな)って原形不定詞の形になっているのがわかりますね。
どの例文も、「先生が生徒に」や、「コーチが選手に」「経営者が部下に」といった形で、「上下関係」があるのがわかりますね。
上の立場の人から、強制力を伴って行動を促(うなが)す時に”make”を使うわけですね。
let
使役動詞の”let”は「許可」の意味で「〜させる」を英語で表現します。
例文を見ながら、「許可」の意味で使われる「〜させる」について見ていきましょう。
【例文】
- The teacher let the students ask questions freely.
先生は生徒たちに自由に質問させた。 - The teacher let the students use their phones during the break.
先生は休憩時間に生徒たちが携帯を使うのを許した。 - The CEO let the employees work remotely to improve work-life balance.
CEO(最高経営責任者)はワークライフバランスを改善するため、従業員のリモートワークを許可した。
例文を見ると、”make”の「〜させる」と違って、使役動詞のletは「強制力」がないことがわかりますよね。
1.の例文では、先生は生徒に「質問(ask)」することを「強制」はしてないですし
2.の例文でも、先生は生徒に携帯電話を「使う(use)」ことを「強制」していません。
3.の例文も、責任者が従業員の「リモートワーク(work remotely)」を「強制」していませんよね。
使役動詞の”let”が、「許可」をしている意味合いで「~させる」を表現しているわけですね。
have
使役動詞の”have”は「お願い」の意味で「~してもらう」を、「指示」の意味で「~させる」を英語で表現します。
使役動詞の”have”で「お願い」を表現するときは、「相手の厚意でやってもらう」ニュアンスで、「指示」を表現するときは「業務や作業を指示する」ニュアンスで使われます。
上述した”make”ほどの強制力はないイメージですね。
【例文】
- She had her assistant call the client.
彼女はアシスタントにクライアントへ電話させた。(指示) - I had him fix my bike.(お願い)
私は彼に自転車を直してもらった。 - He had the waiter bring some water.(指示)
彼はウェイターに水を持って来させた。
知覚動詞
不定詞でtoがつかない「原形不定詞」を使う場面として、「知覚動詞」も挙げられます。
「知覚動詞」も、使役動詞のように「O(目的語)がC(補語)するのをV(知覚動詞)する」という形で使われます。
補語(C)にあたる不定詞の部分が、「原型不定詞」となるので「動詞の原形」になるわけですね。
原形不定詞を使う知覚動詞として、主に以下の5つが挙げられます。
- see(見る)
- hear(聞く)
- feel(感じる)
- watch(観る)
- notice(気づく)
知覚動詞は主に五感で感じたり、気がつく時に使われる動詞を指し、中でも上述した5つが「原形不定詞」を使うイメージですね。
【例文】
- I saw my friend drop his phone into the pool.
友達がプールにスマホを落とすのを見たよ。 - I heard my brother talk in his sleep last night.
昨夜、弟が寝言を言うのを聞いた。 - We watched the workers install the new equipment.
私たちは作業員が新しい設備を設置するのを見た。 - He felt the ground shake during the earthquake.
彼は地震で地面が揺れるのを感じた。 - They noticed the thief run out of the store.
彼らは泥棒が店から走り出すのに気づいた。
まとめ

この記事では、原形不定詞について以下の点からお伝えしました。
- 原形不定詞とは、”to”を伴(ともな)わずに「動詞の原形」で不定詞を表す文法要素
- 原形不定詞は、一部の使役動詞と一部の知覚動詞に伴って使われる
- 原形不定詞を伴う使役動詞は主にmake, let, haveが挙げられる
- 原形不定詞を伴う知覚動詞は主にsee, hear, watch, feel, noticeが挙げられる
この記事でお伝えした内容が、あなたの英語学習をより充実したものにできれば幸いです。
【関連記事】




